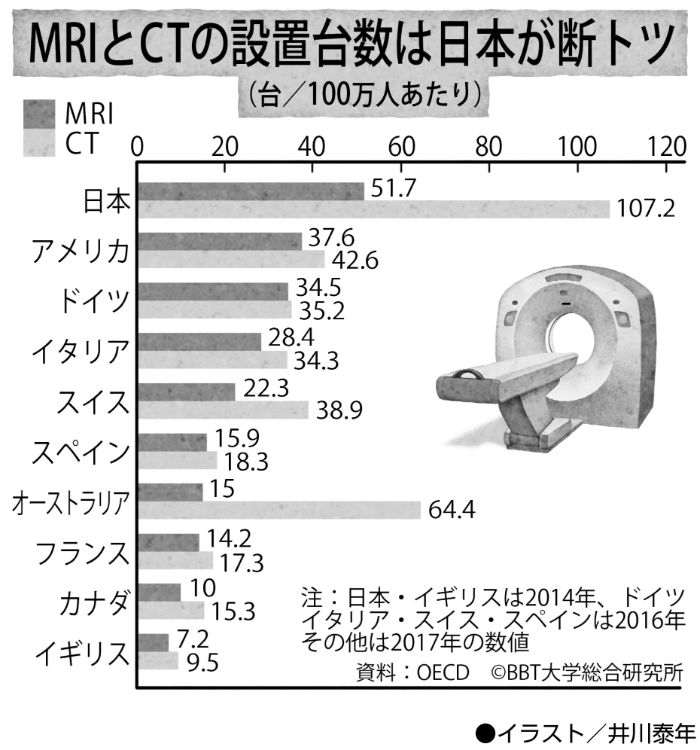MRIとCTの設置台数は日本が断トツ
さらに、製薬業界や薬局の合理化も不可欠だ。前述した2017年度の概算医療費の内訳を見ると、「調剤」が7兆7000億円で全体の18.3%を占めている。これまた自己負担が少ないということで、多くの人が市販の「OTC医薬品(大衆薬)」も、病院で医師に処方箋を出してもらい、調剤薬局で購入している。それを服用しないまま残って何の薬か分からなくなり、また病院に行って同じ薬を処方してもらったりしている。だから調剤費用が異常に膨らんでいるのだ。
そもそも日本は医師の処方箋がなければ購入できない「医療用医薬品(処方薬)」が多すぎる。たとえば、痛風治療薬の「ユリノーム」や花粉症対策の「クラリチン」などは海外ではOTC医薬品だが、日本では医療用医薬品だ。そういう例は他にもたくさんあり、なかにはネットで海外から簡単に購入できる医療用医薬品もある。つまり、日本の医薬品に対する規制は形骸化しているのだ。
また、薬局と薬剤師も多すぎる。厚労省の調査によると、2017年度末時点の薬局数は5万9138軒で前年度末より460軒増加し、2016年末時点の薬剤師数も30万1323人で前々年末から1万3000人以上増えている。
◆AI導入でコスト削減
薬局は厚労省の規制により、基本的に1日平均40枚の院外処方箋に対して1人以上の薬剤師を配置しなければならない。だが、今や事実上、薬剤師はあまり必要なくなっている。なぜなら、医療用医薬品の大半は最初からパッケージングされているからだ。薬剤師が「調剤」しなければならない薬は、極めて少ないのである。つまり、厚労省が規制を緩和し、AI(人工知能)を導入するなどして薬局の調剤を機械化すれば、薬剤師を減らしてコストを大幅に削減できるのだ。