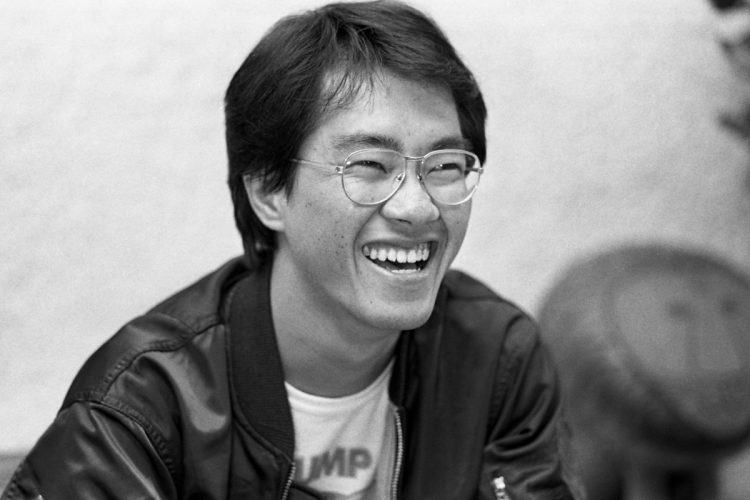年金制度改正で「繰り下げ」の上限年齢が引き上げられ、「繰り上げ」時の減額率が縮小された(イラスト/大窪史乃)
6月15日、今年度最初の公的年金の支給日を迎える。だが、多くの人はこの日初めて、4月よりも受給額が減っていることに気づくだろう。
年金は2か月分がまとめて振り込まれるため、前回の支給日である4月15日に受け取った分は、2月分と3月分。つまり、4月に受け取ったのが、昨年度の最後の年金だったのだ。
「年金博士」として知られる、ブレイン社会保険労務士法人の北村庄吾さんが解説する。
「公的年金の受給額は現在2年連続で下がっており、今年度の公的年金の受給額は、前年度から0.4%引き下げられています。現役世代の賃金が下がったため、マイナス改定となりました。この先もマクロ経済スライドで調整されていくため、受給額は目減りし続けるとみるのが妥当でしょう」
コロナ禍にウクライナ問題と世界的に不透明な状況が続く中、近い将来に給与が増える見通しが立つとは到底思えない。
しかし今年4月以降は、将来のお金に直結する年金の制度改正が目白押し。しっかり把握しておけば、この先受け取る年金を守れるどころか、増やすことも不可能ではない。