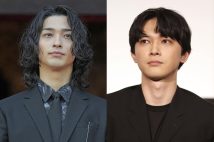公判は福岡地裁で行われた(時事通信)
「心菜のためならできることはなんでもしてあげたい」
その後、心菜さんは生命の危険もあった肺炎を2度経験。そこで夫婦は、呼吸器のチューブを、ケアが容易となる喉からの挿入とする切開手術を決断する。出産当初は予後が厳しいという意見から、「手術で娘を傷つけたくない」とためらっていたが、心菜さんの「生命力の強さを感じた」ことから手術に踏み切った。
出産から2年ほど経ったころ、それまで1時間に数度鳴っていた呼吸器のアラームが、機器を変えたことにより半減し、自宅で看られると感じるようになった。その後、被告人は約10か月病院に寝泊まりして、機器の使い方、急変時の対応などを学んだ。
夫も、心菜さんを家に迎え入れることに賛成。家族間の意見の相違から離婚する家庭もあるというが、訪問ヘルパーからも「こんなに完璧にこなせる父親は初めて」と言われるほど、夫も積極的にケアに取り組んでいた。家に迎え入れてからも、平日に仕事から帰ってきてから、夫が深夜の体位交換を引き受けることもあったという。
弁護人が、被告人の日々の介護の様子を詳細に確認した。夜でも続く2~3時間おきの体位交換、24時間体制の血流の注意、痰の管理、食事、排泄など、被告人の1日の動きはとても書ききれない。日常で被告人がどれほど心菜さんに時間と労力をかけていたかが伝わってきた。
しかし、それ以上に説得力があったのが、被告人の話すトーンだった。
心菜さんの介護について話す被告人の言葉は、明らかにハキハキとしていた。他の質問の回答では「心菜のためならできることは、何でもやってあげたい」とも答えている通り、心菜さんと過ごした日々は、大変ながらも充実した時間だったのだろうと感じられる様子だった。