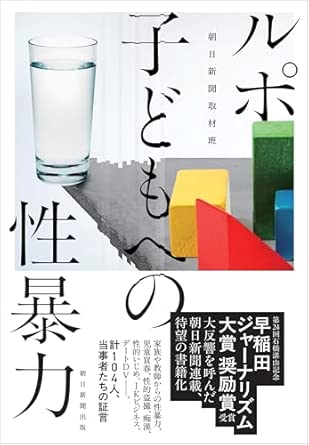法廷で争う際には「証拠」の“信用性”が重要だという(イメージ)
立件の壁、低くするには?
少し古いが、法務省が明らかにしているデータによると、検察が2018年度に「嫌疑不十分」として不起訴にした性犯罪は548件あり、そのうち被害者に障害があったケースは61件だった。不起訴事件の、障害がある被害者60人の供述の信用性については、「客観証拠などと整合しない」17人、「虚偽供述や記憶変容の可能性がある」11人、「看過しがたい変遷がある」10人(複数該当あり)だった。
つまり、不起訴の理由としては記憶の変容や供述の変遷など証言の信用性が疑われるケースが少なくなかった。
そのため、供述の変容や変遷を防ぎ、事実を確認する手法として、警察、検察、児童相談所(児相)が協同して面接する「司法面接」の手法が取り入れられつつある。最近は検察庁が「代表者聴取」という言い方をしているが、もともとは「司法面接」「協同面接」と呼ばれていた。
司法面接は、子どもの虐待をめぐっては2015年から取り組みが始まっている。児相と警察、検察の3者が協力し、性暴力や虐待が疑われる初期の段階ですぐに聴取する。何度も聴かれることによる子どもの記憶の変容や精神的な負担を防ぎ、事実を解明するのを目的に導入された。2020年度に子どもに対して実施された件数は2124件、うち85%を占める被害者聴取の6割近くが性犯罪事案だった。
検察庁は2021年春から、全国13カ所で知的障害などのある人が被害に遭った性犯罪について検察と警察が協力して聴取するモデル事業を実施、同じ年の9月末までの半年間で89件実施し、うち59件が18歳未満だった。ただ、この「代表者聴取」のあり方については問題点を指摘する声もある。
障害のある子どもも含む子どもの性被害を数多く担当している弁護士の芹澤杏奈さんは「代表者聴取は捜査のためだけのものではないはずだが、捜査のためだけになりがちで、100%被害者に役立つようには活用されていない」と問題点を指摘する。
芹澤さんによると、代表者聴取は録音録画されることがほとんどだが、不起訴になると被害者が録音録画媒体の開示を受けることは難しい。起訴されても、裁判で検察が証拠請求して初めて代理人がとう写を請求できる。そうした状況に対して、芹澤さんは「聞き取りの内容は、その後の支援にも利用できるようにするべきで、制度設計が間違っている」と指摘する。現在は検察官が聴取することが多いが、検察、警察、児相が協力した上で、専門性を持った中立の立場の人がインタビュアーを務め、その結果を被害者を支援する立場の人がみな使えるようにすべきではないかと訴える。
また、聴取した内容が証拠採用されても、録音録画につく反訳(文字起こし)のみが証拠になってしまうこともある。「障害のある人や子どもは身ぶり手ぶりなど非言語の表現もしている。裁判官には録音録画をぜひ見てほしい。聴取にかかわった関係者もきちんと見るべきで、それが、供述弱者である障害者についての理解を深め、全体として立件の壁を低くする土壌につながっていくと思う」と芹澤さんは話す。
(第3回につづく)