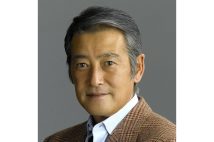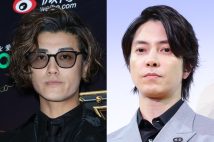教室をどうするか(写真:アフロ)
全国の公立小中学校で、発達障害により「通級指導」を受けている児童・生徒が初めて9万人を越えていることが初めてわかった。この20年あまり間で7倍以上増えた。その対策をコラムニストのオバタカズユキ氏が考える。
* * *
18年前より「キレイ事は一切抜き」の精神で『大学図鑑!』という大学案内本を毎春出している。このところは、自著だけでなく、進学や教育分野のプロを著者とする書籍の企画・編集にも勤しんでいるのだが、そのからみで出会った教育関係者たちから頻繁に聞かされる件がある。「発達障害の増加」についてだ。
例を挙げればキリがないのだけれども、中学生になっても授業中の立ち歩きが治まらないばかりか、「ちょっと目を離した途端、教室の床の上を赤ちゃんハイハイしているんですよ!」といったエピソードが続出する。そのハイハイ君はADHD(注意欠陥多動性障害)と診断された子だそうだが、他にも読み書きなどに困難を抱えるLD(学習障害)、自閉症などいくつかの診断名がある。そうした発達障害児に振り回されて、先生方が実に大変な思いをしているようなのだ。
この問題は近年急速に拡大している感があり、先日も、全国の公立小中学校で「通級指導」を受けている児童と生徒が、初めて9万人を超えたという文部科学省の調査結果が報じられた。
通級指導は、〈比較的軽い障害がある児童・生徒が、特別支援学校や特別支援学級ではなく通常学級に在籍しながら、各教科の補充指導などを別室で受ける制度〉(毎日新聞の記事より)のこと。重い障害児についてはあまり話題にならず、もっぱら〈比較的軽い障害〉の増加が注目されている。
文科省の同調査では、昨年5月1日の時点で通級指導を受けている子が、前年度比6520人増であった。調査を始めた1993年度との比較では、なんと7.4倍増。潜在的には、通級指導が必要な子はプラス数万人いるとの説もある。なにやらオオゴトだ。
ただし、この問題は、実態の把握からして難しい。はたして発達障害児は本当に増加しているのか、増えているならそれはなぜか。いまだ定説はない。
発達障害児は増えている。そう見る向きの中には、増加理由として、ワクチン接種やサプリメントなどの害、空気中の汚染物質の影響を指摘する人もいる。完全母乳哺育による栄養不足が原因だと言う医師もいるし、父親の高齢化との関連性が明らかだとする論文もある。玄人たちの間でも見解がバラバラだ。とても私が正解を選べる話ではない。
けれども、1993年度から2015年度の僅か20年余りの間に、通級指導の子が7.4倍にもなったという事実は、上記のような理由からだけではとても説明しきれない気がする。そこには統計のからくりがあるはずだ。と、ずっと思っていたのだが、今回、文科省自ら〈学校現場での理解が広がり、把握が進んだ結果とみている〉という説明をしていた。ならば、腑に落ちる。