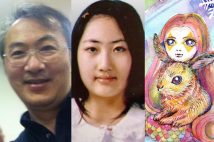カットによりさまざまに変化するデザイン
NHK大河ドラマ『西郷どん』で注目を集めている鹿児島県。その北部にあるさつま町は、薩摩切子(さつまきりこ)のふるさとでもある。
ガラスの表面が綿密にカットされ、色のグラデーションが美しい薩摩切子。初めて作られたのは“西郷どん”の時代にさかのぼると、『薩摩びーどろ工芸』広報の上えりかさんは言う。
「1846年、薩摩藩の第10代藩主・島津斉興が製薬館を創設。江戸から職人を招いて薬品用のガラス器づくりを始めました。その後、1851年に島津斉彬が11代藩主に就任したのを機に、海外との貿易品として“薩摩切子”の製造が始まり、日本で初めて紅色ガラスの発色に成功しました。当時の日本は欧米諸国から開国などを迫られていた時期、薩摩藩でもさまざまな産業が行われていたのです」(上さん・以下同)
薩摩切子は、当時、篤姫の嫁入り道具にも使われたといわれており、今では鹿児島県を代表する工芸品の1つだが、30年以上前までは、幻の存在となっていた。
「斉彬が急逝後、薩摩切子の産業は縮小されました。また、1863年に起きた薩英戦争で、薩摩はイギリスから攻撃を受け、多くの薩摩切子の工場消失につながります」
薩摩切子が盛んに作られていたのは、わずか20年足らずというが、1975年、長らく途絶えていた技術を大阪の『カメイガラス』が職人を集めて復元。そして今から30年ほど前の1989年には、鹿児島でも当時、わずかに残っていた現物や資料をもとに、再び職人たちが薩摩切子を復元し、今に至る。職人は比較的若く、30代が中心。斬新なデザインも豊富だ。
「薩摩切子の特徴は、色のぼかしにあります。透明なガラスに厚さ1~2mmの色ガラスをかぶせて、カットを施すことで、色のグラデーション、つまり、ぼかしがつくのです」
ぼかしはカットの深さや大きさによって変わるため、ダイナミックなものから、繊細なものまで、さまざま。
「現在は、伝統的な技術を受け継ぎつつ、薩摩黒切子・薩摩ブラウンなどの新しい色やカットなどの文様も取り入れ、現代的な薩摩切子の製作も行っています」
時代の流れにより、進化を続ける薩摩切子。赤や青などカラフルなものが主流だが、最近は、黒一色の薩摩黒切子も人気だ。
※女性セブン2018年8月16日号