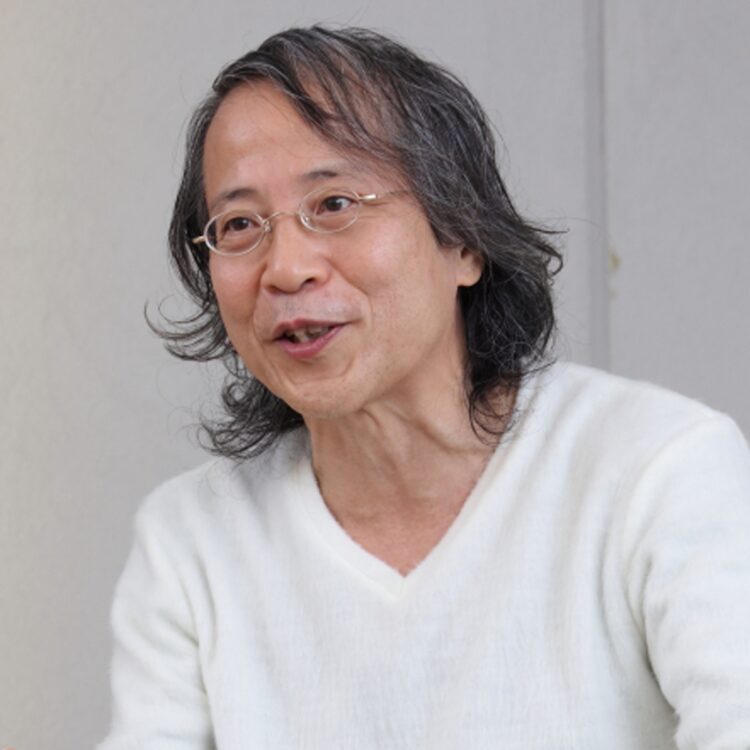自身も「学校に子どもを合わせようとする日本の教育に苦んだ」という
西郷:そうなんです。例えば、校則で靴下の色が白と決まっていたとします。それに違反した生徒を、教員は叱ります。でも実は、なぜ白い靴下でないとダメかを、注意した教員も論理的に理由を説明できず、「だって、校則に書いてあるから」としか言えないのです。意味のない校則があることで、子どもを取り締まろうとして教員の仕事は増えるし、子どもは傷つく。校則一つひとつを検証してみたら、本当に必要なものなんて、ひとつもなかったんです。
──子どもの村学園の堀真一郎学園長が、「“自由には責任が伴う”などと言うと、子どもたちが大胆に行動することが難しくなってしまう」と話していましたね。
オオタ:“責任が伴う”なんて、自由にさせないためにある言葉ですよね。これからの時代、自由な発想でイノベーションする社員がいないと、会社の経営が行き詰まるはずなのに。
西郷:よく、「将来のためにいまがまんしろ」と子どもを抑えつけますが、考えてみてください。おとなになってからも、そう言われることの連続です。だとしたら、したいことをしないで、死ぬまで人生、ずっとがまんし続けなくてはいけません。
服装だってそう。「中学生らしい服装」なんてよくいいますが、はたしておとなの思う地味な装いが本当に中学生らしいでしょうか。かわいく着飾ったり、華やかなものを着る方が、よほど中学生らしいはずです。
自由な学校は成績が悪いという思い込み
──「規則がなくて、楽しいだけじゃ成績が上がらない」と世間は批判しませんか?
西郷:そうなんです。でも実際は逆なんですよ。これは調査からもわかっているのですが、楽しんでいる生徒、自分の感情を押し殺さずに出せている生徒の方が、成績もいいんです。実際に、桜丘中も区内の学校に比べて、部活動も勉強も成績がよかったんです。
──「いい学校=勉強ができる」というものさしで測られることが多いように思います。
オオタ:映画でも、子どもの村学園を卒業した子どもたちは高校でも大学でも成績がいいということに触れているのですが、本当はそのことについて触れるかどうか迷ったんです。「学校が楽しかった」というのがいちばん大事なはずなのに、そこが無視されてしまっている。
西郷:大阪市のように、全国学力テストの結果を教員給与や学校予算に反映させるというのは論外です。
オオタ:いまはAIの登場で、産業構造も社会構造も変化しています。いい成績でいい大学を出て、いい企業に入ったからといって、その会社が10年後も存続しているかどうかわからない時代ですからね。