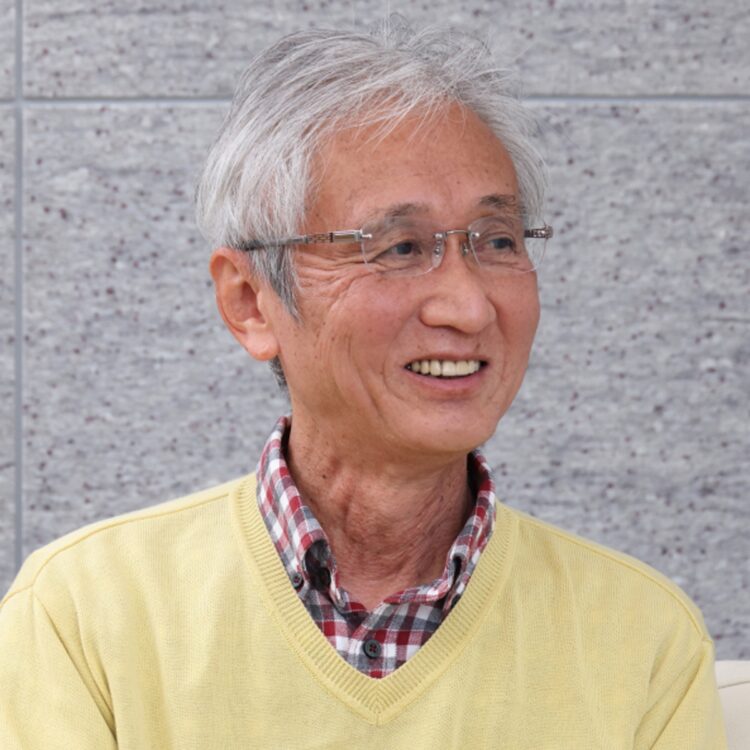意味のない校則があることの弊害を訴える
西郷:アップルの創始者スティーブ・ジョブズは、大学中退です。世間で言うところのエリートではありません。アップルの時価総額は340兆円ですが、これは日本の国家予算(一般会計歳出)の3倍以上です。もしジョブズが日本人だったら、国家予算がとてつもなく増えていたかもしれない。みなさんの給与も倍になっていたかもしれませんね(笑い)。
オオタ:ジョブズが、発達障害のひとつであるアスペルガー症候群だったというのは有名な話です。ジョブズは子どもの頃はカリグラフィ(欧文文字を美しく書く技法)ばかりやっていたといいますが、日本にいたら、「そんなことをしている暇があったら計算問題を解け!」と叱られたでしょうね。
西郷:でも社会を変えるのは、ジョブズのような人の方です。決して、おとなの言うことに従ってきた子じゃない。
オオタ:映画にも登場してくださっている文化人類学者で明治学院大学名誉教授の辻信一さんのゼミでは、これまで子どもの村学園の卒業生が何人か学んでいるそうです。
──辻さんは、「子どもの村学園出身の子は、探究心と質問する力がある」と話していますね。
オオタ:そのうちの1人は非常に優秀で、明治学院大学の卒業生総代になったそうです。
西郷:映画の中で、前の学校で発達障害と決めつけられた子が出てきましたが、子どもの村学園に転校したら、薬をのむ必要がなくなった。あれはとても印象的でした。
オオタ:日本の教育は、学校に子どもを合わせようとする。私も苦しみましたが、そこからはみ出した子は救われません。
西郷:変えるべきは子どもじゃない。子どもが過ごしやすい環境にしてあげることこそが、本当は必要なんです。
「好き!」と思えることをすれば脳が発達する
オオタ:桜丘中や子どもの村学園が、まさにそうですね。
映画では、脳科学者の茂木健一郎さんにも登場いただいているんですが、彼は「脳神経間のシナプスという結合部分が変化することが学習だ」と言っています。そのために主要教科だけを学ぶのは狭い考え方で、むしろ子どもたちが「好きだ!」と思えることを熱中してやっている方が、脳にとっていいそうです。