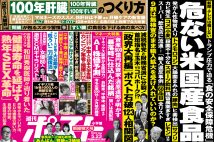日本人のマンガ好きを再認識させた小学館ビルのラクガキ
8月に、小学館本社ビル(東京・千代田区)取り壊しに際して行なわれたマンガ家たちによる「ラクガキ大会」。同月9日に25人の漫画家によって描かれて以降、連日ビルの外に人垣ができるほどの大きな話題を呼び、22日にはさらに84人の漫画家が参加。一般公開された24、25日には8000人のファンが日本各地から訪れた。
この“事件”で、日本人がいかにマンガ好きか、ということが再認識されただろう。もちろん、皆が皆、ラクガキで描かれた「絵」だけを好んでいるわけではない。マンガを構成する重要な要素のひとつ「台詞」に対しても、愛着を持っている人は少なくない。『マンガの食卓』(NTT出版刊)などの著書があるマンガ解説者・南信長氏(48)が語る。
「昨今、『スラムダンク』、『ワンピース』(集英社刊)『カイジ』(講談社刊)などの人気マンガの名言は単行本になっており、マンガの持つ言葉の力がクローズアップされています」
こうした背景に加えて、最近では、Twitterなどでマンガの名作台詞がつぶやかれることも多く、知らず知らずのうちにマンガの名言を目にする機会も増えている。
いわれてみれば、『北斗の拳』(集英社刊)でラオウが語った「我が生涯に一片の悔い無し!!」や、『スラムダンク』(集英社刊)で三井寿が語った「安西先生…!! バスケがしたいです……」など、誰もが知っているような名言は数多い。これも日本人がいかにマンガ好きかを表わしているといっていいだろう。
マンガの名言が多くの日本人に受け入れられるのは、なぜなのか。前出・南氏が解説する。
「1959年に『週刊少年サンデー』(小学館刊)、『週刊少年マガジン』(講談社刊)が同時創刊し、1970年代以降には、大学生がマンガを読むようになったことが社会問題になりました。当時、マンガで育った大学生は、今や還暦をすぎており、大人になったらマンガは卒業、ということはありません。
さらに最近では、他人に影響を与える言葉の発信源が、どんどん身近になっているんです。Twitterなどで知人の意見を参考にする、書店では書店員さんのお勧めを参考にする。こうした目線の近い人の意見こそが重視される時代なのでしょう。マンガキャラクターの言葉が親近感をもって、すっと受け入れられるのは、自然な流れかもしれません」
そうした中で、この10月から、缶コーヒー『FIRE 挽きたて微糖』の缶の側面にも「心の火を大きくする名言マンガ」と題して、マンガ名言が掲載されている。
「コーヒーは火でおいしさを引き出します。缶コーヒー『FIRE』を通じて、“働く人の心に火をつけたい”という思いから、今回の企画も生まれたんです」
こう語るのは、キリンビバレッジ・マーケティング部『FIRE』担当の大塚宗太郎氏(40)。
「マンガ名言には、働く人たちのやる気を起こさせる力が強い、と注目しました。缶コーヒーを飲まれる30~50歳の方々の中には、根強いマンガファンが多い。そうした方々に、懐かしいマンガの名言はしみわたるのではと考えています」
缶コーヒー『FIRE 挽きたて微糖』に掲載されるマンガ名言は30種類。そこに紹介されている以下のような名言(いずれも小学館刊のマンガより)は、たしかに働く人たちをやる気にさせる力があるように思える。
〈目立たないけど、会社の為に役に立ってる人材っているものです。〉(『釣りバカ日誌』64巻42頁)
〈仕事は人のためです。人のために良かれと思ってやるのが仕事だと思う。〉(『総務部総務課山口六平太』42巻41頁)
〈でもそれはめぐりあわせで、必ず陽の当たる時が来るって…がんばってくださいね。〉(『めぞん一刻』12巻58頁)
〈他人にやらされてた練習を努力とは言わねえだろ。〉(『MAJOR』31巻119頁)
その他、『がんばれ元気』『三丁目の夕日』『東京ラブストーリー』など馴染みのあるマンガキャラクター達の含蓄ある台詞が“おっ”と思わせてくれる。名言の脇にあるQRコードをスマートフォンや携帯電話で読み取ると、マンガを1話、無料で読むことができる。
「企画を上司に説明に行くと、非常に受けが良かったんです。その時、これはいけると思いました」(大塚氏)
大塚さんのチームメンバーは、オフィスの机にコミック単行本を数十冊置き、ひたすら名言を探しつつ読みまくったという。
仕事のブレイクタイムに、すっきりした後味の微糖コーヒーを味わいながら、懐かしいあのマンガを1話読んで、心に火をつけてみてはいかがだろうか。