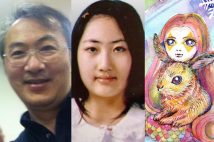和食文化を牽引する寿司は、海外でも人気(Getty Images)
いま食べるべき魚を消費者が選ぶ時代
日本が誇る豊かな海を守るべく額に汗して行動する人たちのために、海から遠く離れた場所にいる私たちができることはあるのか。岩手県漁協女性部連絡協議会会長で、重茂漁業協同組合女性部部長の盛合敏子さん(68才)は、何よりもまず「海はきれいなものだ」と認識してほしいと語る。
「私は週1回必ず海を見に行きますし、皆で海岸を掃除することもありますが、残念ながらいまでも海にゴミを捨てる人がいるのが現状です。海がきれいなものだと認識してもらえれば、釣りをするにしろ海岸で遊ぶにしろ夏に泳ぐにしろ、その場にゴミを捨てて帰ってしまうようなことはなくなるのではないかと思います」(盛合さん)
公益財団法人「海と渚環境美化・油濁対策機構」の専務理事として環境保全に取り組む坂本幸彦さんも「関心を持つことが重要」と声を揃える。
「日本人のモラルは昔よりよくなってポイ捨てをする人も減ったし、リサイクルも進んでいます。それでも数は多くありませんが、心無い人が日常的に不法投棄をしたり、ゴミを道路脇の側溝や植え込みに捨てたりしています。
だからこそ大切なことは、一人でも多くの人が身近な環境問題に関心を持つことです。そのうえで一人ひとりがゴミの分別を心がけ、洗剤は適量を使ったり環境に配慮した商品を買ったりするなど、日常のなかで少しずつやれることを増やしていくことが大切です。NPOや自治体が実施しているゴミ拾いに参加してみるのもいいでしょう。1回でも2回でも、一人ひとりが自ら手を動かしてゴミを拾うことで、環境問題はいい方向に進むと思います」
食卓に並べる魚を選ぶ際も、立ち止まって考えたい。牧野さんはいう。
「生態系の変化は人間にはコントロールが難しい部分も多々あり、自然に人間が寄り添おうとする姿勢が欠かせません。たくさん獲れる旬の魚をおいしくいただくことを心がけてほしい」(牧野さん)
その際、判断材料となる情報を知ることも必要だ。
「『MELマリン・エコラベル・ジャパン』や『MSC海洋管理協議会』など、水産庁や環境団体などが推進するエコラベルがついた水産品は、海洋環境の保全に役立ちます。また、米NPO『セイラーズフォーザシー』の日本支局が発行する『ブルーシーフードガイド』のホームページを見れば、食べていい魚と食べない方がいい魚が一目瞭然です。
例えば現在はうなぎや黒まぐろは希少ですが、かつおや真いわしは潤沢に獲れる。欧米はレストランでこうしたガイドを見てオーダーすることも多い。日本でもこうした情報を有効活用し、きちんと管理された魚を積極的に食べ、資源を循環させることが求められます」(牧野さん)
豊饒の海を守るために、できることから始めたい。
※女性セブン2021年12月9日号