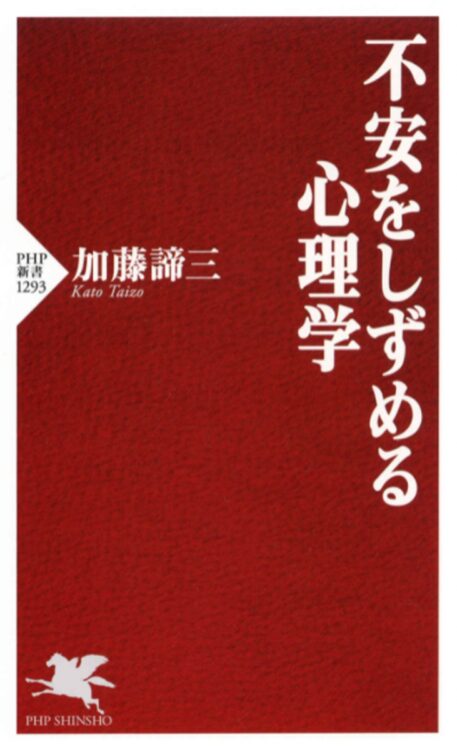「不安」と真正面から向き合った『不安をしずめる心理学』
「不安の心理を理解せよ」というのが、本書の提言だ。
生きてきて、これまで一度も不安を感じたことがないという人はおそらくいないだろう。芥川龍之介が「唯ぼんやりした不安」という言葉を残して自死したことはよく知られている。われわれにとって、なじみ深い感情である一方で、どこかあいまいで、つかみどころがない。
「不安の問題は、感情的健康と深くかかわっています。たとえば30歳の男性が2人いたとします。母親との関係で満たされて30歳になった人と、まったく満たされずに30歳になった人とでは、感情的健康がまったく違っています。30歳だけど心はまったくの幼児という人もいます。
肉体的健康だと、39℃の熱があれば、自分も周りも健康ではないと考え、そこに不一致はありません。ですが感情的健康のほうは、自分と周りの意見が一致しないことも多く、健康ではないと周りが感じていても、本人は気づいていないことがあります」
不安の感情は3つの形で人間関係のトラブルに表出
不安の感情は、人間関係のトラブルに表れるという。
「どういう形で出るかというと、1つめは攻撃的になる場合。なんだか喧嘩腰の人っていますよね。2つめはその逆で、妙に迎合する人。迎合的なんだけど、無意識に敵意を抱いている。3つめが、とにかく人と接するのが嫌で引きこもってしまう場合。つまり、不安な人というのは、普通に人と接することができなくなっているんです。
なんとなく不安だという人は、自分が意識していないところで問題を抱えていることがあります。社会的に大きな問題になっている引きこもりや児童虐待も、根源にあるのはこの不安の感情です」
外面はいいのに、家に帰ると妻に向かって暴君のようにふるまう夫がいる。典型的な昭和の亭主関白のようだが、これも不安が根底にあると加藤さん。
「私はもう60年近く、ラジオの『テレフォン人生相談』(ニッポン放送系列)を担当しているんですけど、『夫が自分の返事の仕方一つで、ものすごく怒る』という悩みを寄せられたことがありました。夫は外面がいいから、誰に相談しても相手にしてもらえない。私が『大変でしたね』と言うと、奥さんは『わかっていただけますか』と泣き声になっていました。
これなんか、『攻撃性の置き換え』ですね。腹を立てている対象はほかにあるんだけど、自分の怒りを意識するのが怖くて、攻撃しても大丈夫だと思っている妻を攻撃対象にしているんです。よく、離婚するときに『性格の不一致』と言いますが、そんなものはなくて、どちらかが、感情的に不健康で不安だというのがほとんどの原因です」