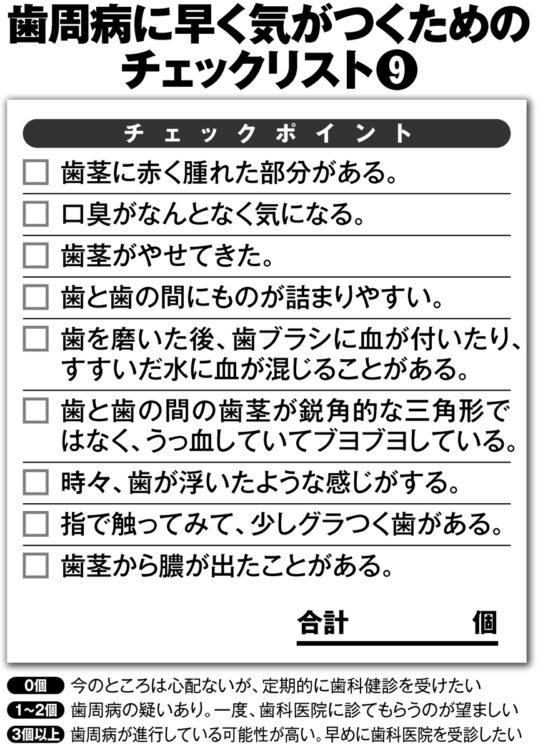歯周病に早く気がつくためのチェックリスト9
「再発リスク」が高い
一方、SRPなどの非外科処置では歯周ポケットの深さが改善しなかったり、歯石やプラークが取り切れない重度の歯周炎の場合、「外科処置(手術)」が必要になる。
「ポケットの深いところや、奥歯の歯根の分かれているところ(根分岐部)まで歯周炎が進んでいる場合、非外科処置では歯石やプラークは取りきれません。こうしたケースでは、麻酔をして歯肉を切開し、歯根の表面を露出させてから、歯石やプラークを取り除く外科処置(手術)を行ないます。歯根の表面を直接見ながら確実にプラークが除去できるため、歯周炎が改善されます」(弘岡氏)
しかし、外科処置では術後に歯肉が大きく下がり、歯が長くなったように見えるデメリットが生じることもある。治療で歯茎の健康が取り戻せても、見た目を元のように戻すのは難しいという。
また、重度の歯周炎で歯を支えている骨などの歯周組織が失われてしまったケースに対して、それらを再生させる「歯周組織再生療法」が選択されることもある。
「20年以上前にスウェーデンで開発され、世界で広く応用されているエムドゲイン療法(幼若ブタの歯胚から抽出されたエナメル基質タンパクを歯根面に塗布して歯周組織の再生を促す治療法)、近年日本で開発されたリグロス(細胞増殖因子を含む薬剤を歯槽骨欠損部に塗布する治療法)があります。それらが適応かどうかは患者や部位によって異なるため、歯科医師が判断します。歯周組織再生療法により重度歯周炎で抜歯が避けられない歯の保存が可能になります。抜歯の前に歯の保存を考えましょう」(弘岡氏)
エムドゲインは自費診療なので5万~20万円、リグロスは2017年から保険適用となり約8000円の医療費負担となる。
どんな治療を選択するにせよ、何より大事なことは「治療後のセルフケア」にある。
日常のプラークコントロールが肝となる歯周病では、一度、罹患した人は再発の可能性が高いとされる。そのため、治療後のケアが重要なのだ。
日本歯周病学会認定歯科衛生士の加藤典氏が言う。
「歯周病の治療は、患者さんと歯科医師、衛生士が共同で行なわないとうまくいきません。まずは患者さん自身が歯周病がどんな疾患かを学ぶこと。そして、歯と歯の間、歯と歯茎の間など、プラークが溜まる場所に特化した磨き方を知り、1日1回は完璧にプラークを落としていただく必要があります。歯間ブラシなどの補助用具も太さなどたくさんの種類があるので、何が必要か、専門家のアドバイスを受けて使っていただきたい」
歯周病は「治しただけ」では終わらない。治療により歯の隙間が開けば歯列矯正が必要になり、抜歯後にはスペースを補う義歯やブリッジ、インプラントなどの補綴治療が必要になることもある。
「抜歯が避けられなかった歯周病患者にインプラントを応用する場合、歯周炎と同じメカニズムで生じるインプラント周囲炎の発症リスクも高くなるので、その予防も考えなくてはなりません。歯周病治療期間は短ければ半年、重度になると2~3年かかるケースもあります。重度歯周病の治療を受けた患者さんは回復した健康の維持のため歯科医院での定期的なメンテナンスが必須です。歯周病の適切な治療法とその後のケアについて、ぜひ理解していただきたい」(弘岡氏)
処置後のケア次第で良くも悪くもなる歯周病治療。歯の状態は「健康寿命」を左右するだけに丁寧に行ないたい。
※週刊ポスト2022年9月30日号