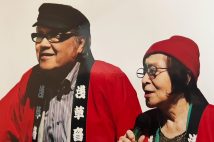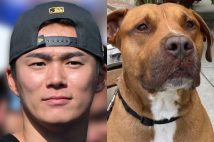小林武彦氏が新作について語る(撮影/国府田利光)
2021年刊行の『生物はなぜ死ぬのか』では死の生物学的な意味を、2023年の『なぜヒトだけが老いるのか』では、人間が繁殖期を過ぎてなお生き永らえる意味を肯定的に問うてみせた、東京大学定量生命科学研究所の小林武彦教授が、シリーズ第3弾『なぜヒトだけが幸せになれないのか』で満を持して挑むのが幸福、すなわち〈「生」の意味〉だ。
そもそも生や死に意味を求めるのも人間特有だが、その人間が自分達が単なる進化の結果として存在する事実に耐えられず、幸せという〈魔法の言葉〉を発明して以降、事態はかえって複雑化したという。
そこで本書では「幸せ」=〈死からの距離が保てている状態〉と定義した上で、この生物学的な「幸せ」を何が感じにくくさせているのかを全6章に亘って検証。すると意外にも原因の1つは、ヒトと類人猿が分かれてから約700万年かけて作り上げてきた遺伝子と現代社会との不適合によることが見えてきた。
「前々作を出した後に、お手紙を頂戴したんです。死こそが進化を促す究極の利他的なイベントだと言うなら、我々老人はさっさと死んだ方がいいんだなって。いやいや、そうじゃない、老いにも進化上の必然性があるんですと言いたくて、前作では私の専門分野でもある老化について書いた。
残るテーマが今回の生で、私はヒトだけが特別という考え方は普段しないんです。あらゆる生物は偶然生まれ、意味も目的もほぼないに等しい。そこでヒトが発明したのが幸せという概念で、肉食動物にすれば今日食べる餌があること、草食動物は今日誰にも食べられなかったことが、究極の『幸せ』なんですよね。だとすれば生きていることが当然になりすぎた人間の幸せも、よりシンプルな形に戻すことでいろんなことがわかるんじゃないかという、これは提案の書でもあります」
元々はこれらの新書を受験生らの理科離れ、生物離れを食い止める啓蒙活動の一環で書き始めたという元生物科学学会連合代表は、わかりやすさや「言い切ること」にも重々心を砕く。
「仮にこれと同じ題の本があっても、結論はボヤっとしたままで終わっていると思う。でも私の本では答えもちゃんと書いているし、どんな人でも読めるように簡単に書くってことは、ボヤっとさせないことなんですね。当然、怒る人はいますよ。でもそこは玄人に怒られるか素人から感謝されるかで、生物って面白いんだと思ってもらうことの方がずっと大事です。本人は多少傷つきますけど(笑)」
例えば〈弥生格差革命〉、略して〈YKK〉なる造語である。著者はまず人類も〈変化と選択〉を繰り返し、森から平原、平野へと移動する中で〈たまたま「よく生きる」ものが選択されて〉きた進化の過程を一通り追った上で、中でも人々の生活環境が一変した縄文~弥生期に注目する。