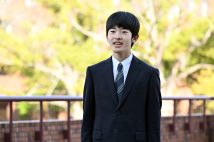1970年代から1980年代にかけて日本全国の温泉観光地に次々と開館した秘宝館は、当時の世相を色濃く反映した施設だったといえるだろう。『秘宝館という文化装置』(青弓社刊)の著者で、北海道大学特任助教の妙木忍氏が解説する。
「秘宝館のひな形を作ったとされる、三重の元祖国際秘宝館のオープンは1972年。当時は『レジャーブーム』『余暇時代』といわれた時代です。個人での車の所有も少しずつ進んではいましたが、まだ旅の中心は大型貸し切りバスによる団体旅行。これが秘宝館ブームを後押しし、最盛期には日本全国に20館以上が存在していました」
妙木氏の秘宝館の定義は、「性愛をテーマにした博物館で、等身大の人形を使い、来館者が参加できるアトラクションが設備される遊興空間」。現在は、前ページで紹介した熱海秘宝館が残るのみである。ちなみにこの定義にはあてはまらないものの、個人的に性のコレクションを展示しているような施設の中には、現存しているものもある。
北海道から九州まで、多くの秘宝館が次々と誕生した背景には、技術の進歩も大きかったという。
「精巧な等身大人形の製作や音響、機械、照明などには高度な技術が求められます。主な秘宝館は一社の企画会社が手がけていました。この会社は映画会社・東宝の出身者が作った会社で、人形の製作から視覚的な演出まで、当時最新の専門技術が多く用いられていたのです」(妙木氏)
一社で複数の秘宝館を手がけていたため、スカートが舞い上がるマリリン・モンローなど、全国に同様の仕掛けを持つアトラクションが複数存在したが、地域にかかわる展示を取り入れるなどして、他館との差別化を図ったという。
「バス旅行の衰退や娯楽の多様化を背景として、秘宝館の来館者数は減っていきました。しかし、江戸時代の春画の芸術性が現代になって見直されているように、今後、秘宝館の芸術性が見直される可能性は大いにあると思います」(前同)
昭和の芸術が再び艶やかに動き出す日はくるのだろうか。
※週刊ポスト2015年2月9日号