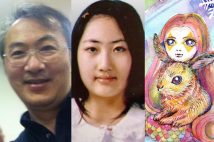一般的に、金利下落局面では次なる上昇局面を見越して、資金を動かしやすい普通預金や、定期預金でもなるべく預ける期間を短くしておくのがセオリーといわれる。
「しかし、今回、日銀がマイナス金利導入に当たってインフレ目標の達成時期を2017年前半に後ズレさせたように、あと1年程度で金利が正常化するとは到底思えません。そう考えていくと、定期預金も1年ものだけでなく、資金を分散させて、一方は2年以上のものにしておくという手も考えられます」(深野氏)
従来の常識を打ち破る「マイナス金利」が打ち出された以上、これまでのセオリーにとらわれない柔軟な発想が求められる。
また、預貯金がマイナス金利にならないとしても、収益が圧迫される銀行が預金者に「負担増」を迫るケースも考えられる。
「ATM手数料や口座管理手数料を上げるようなわかりやすいケースは反発を招きやすいので、やるとはあまり考えにくい。たとえば預金残高や取引状況に応じた優遇サービスで振込手数料を月3回まで無料だったものを2回に減らすとか、目に見えにくい形での負担増はあるかもしれません」(深野氏)
※週刊ポスト2016年2月26日号