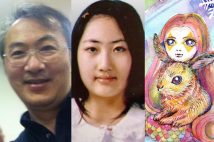埼玉県日高市では線路跡が踏切もそのままに遊歩道に
その一方で、国土交通省は正式な踏切の数をとにかく減らすことに躍起になってきた。近年、踏切数を減少させるために連続立体交差事業に力を入れており、特に東京・名古屋・大阪といった都市圏では高架化・地下化による踏切の除去は急速に進んでいる。
連続立体交差事業は交通渋滞の解消、線路で分断されていた市街地の活性化、踏切事故の防止などが大義名分として掲げられているので、住民からの反対が出にくい。
踏切廃止は鉄道業界の潮流であり、日本全土から次々に踏切は葬られていった。特に、2005(平成17)年頃には開かずの踏切が社会問題化したこともあって、踏切廃止の流れは一気に加速した。最近はペースが鈍っているとはいえ、国土交通省は年間1000件ペースで踏切を廃止していたこともあり、踏切は社会全体から爪弾きにされた。
そんな嫌われ者の踏切でも、特別な思いを馳せる人たちは決して少なくない。
八高線の高麗川駅は近隣に太平洋セメントの工場があり、2001(平成13)年まで貨物列車が行き来していた。専用線廃止後、地元の埼玉県日高市は線路跡地を譲り受けて遊歩道として整備。遊歩道には、往時を偲ぶ踏切が残されている。
同じく阪神電鉄は本線の一部区間を2001年に高架化。そのことで不要になった踏切は、地元に引き取られて近所の公園に移設されている。公園内には、特に踏切について説明する看板などは見られないが、そこに踏切があったことを後世に伝えようとする思いは感じられる。
このほかにも、町内会や自治会、商店街で踏切を引き取って記念碑的に踏切を残しているケースがある。
急いでいるときに開かずの踏切につかまって、歯がゆい思いをしたことがある人は多いだろう。心の中で「踏切なんて、なくなってしまえ」と毒づいた経験は誰もが持っているだろう。
しかし、いざ踏切がなくなると、途端に寂しくなる。まるで、大事なあの人のような存在――それが、踏切なのかもしれない。