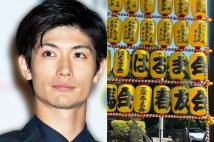──その問題に対して、私たちができることはなにかありますか?
汐見:保育の当事者たちで職場研修を行うことをどこでも慣習化することがまず必要ですが、保護者の方も保育者ともっとコミュニケーションを深め、実際の保育を観察したり議論したりして、本当にいい保育とはどういう保育かを判断する目を肥やさないとダメでしょうね。私は、保育者と親が共に学び交流を深めるために『エデュカーレ』という雑誌を主宰していますが、その雑誌で8年間続いた人気連載マンガが最近、書籍になりました。『じんぐるじゃむっ』といいます。このマンガは、保育の内容、さらには「質」とはどういうことかをマンガで分かりやすくまとめてくれているので参考になると思います。
──情報に積極的に触れることが大切ですね。
汐見:一般の人だけでなく、保育行政に司る行政官や政治家も、もっと本物の保育を行なっている幼稚園、保育園、子ども園で視察をしたり、関係書を読み込んで、保育の意義を理解してほしい。そうでなければ、保育はいつまでも「数」を増やすことに関心が向かい「質」の議論の方には進まない。すると、保育が劣化しかねません。私は保育に関心が強まっている今だからこそ、量も質も議論される世の中になることを願います。私自身も引き続き、できる限りお役に立ちたいと思っています。