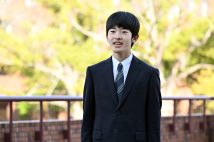これらの統合では、途中で破談などという事態になりそうなケースもあったという。学校法人同士の統合では、文化、伝統、校風が違う。大学の中での教員の立場も違えば、教職員の待遇も異なる。学校法人全体の統合は時間がかかり、一筋縄ではいかない。
慶應義塾大に薬学部、関西学院大に教育学部、上智大総合人間科学部の中に看護学科が新設された。統合することで、新学部・学科設置のために新しく教員を集める必要はなく、キャンパス、校舎もそのまま手に入り、学部新設の申請の必要もない。統合された大学のほうではブランド大学との統合で、経営が安定し学生募集に頭を痛めることがなくなる。
新設された慶應義塾大薬学部の場合、それまで私立大難易度トップだった東京理科大薬学部を抜きトップの難易度になった。慶應ブランドのなせる業だ。総合大学にない学部を持っていて、さらに必要とされたから統合され、両者とも満足いく結果となった。
来年からは桃山学院大などを経営する学校法人桃山学院が現プール学院大学の運営を引き継ぎ、名称が桃山学院教育大に変わる。
ただ、一般的に同じ学部を持つ大学同士の統合は難しく、統合される学校法人に付属校などがある場合も厳しい。そうなると、統合が可能な学校法人は限られてしまう。その点、学部の譲渡ならスムーズにいきそうだ。経営の厳しい大学から、設置したいと構想する学部を譲渡してもらう。譲った大学はその資金で改革に取り組むということになる。
さて、これにはどれほどニーズがあるのだろうか。特に東京では、23区内での大学・学部の新設は、今後、認められなくなる。地方創生のために、学生の東京一極集中を避けるのが狙いだ。そうなると、有力大学は学部新設が厳しくなるためニーズは高い。