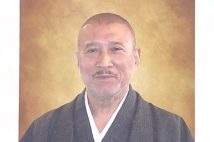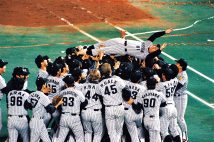高野山奥之院へは南海高野線終点から高野山ケーブルに乗り換える(時事通信フォト)
遡ること50年前の1969年に、大阪市営地下鉄(現・大阪メトロ)が千日前線を開業。そのときに桜川駅は開設された。そして、2009年に阪神も桜川駅を開業している。
駅名が異なるので気づきにくいが、汐見橋駅と桜川駅は乗り換えの利便性が少しずつ認識されるようになった。それが乗降客増という数字にも表れている。
汐見橋駅と桜川駅という駅名の不統一を解消すれば乗換駅としての認識も広がり、さらに利用者は増えるはず。
汐見橋駅が開設されたのは1900年。当時の駅名は道頓堀駅だが、翌年には汐見橋駅に改称。対して、桜川駅は大阪市営地下鉄(現・大阪メトロ)が1956年、阪神が2009年に駅を設置した。歴史的に見れば、汐見橋駅は大先輩にあたる。
「桜川駅は他社の駅になりますので、駅開設時に『汐見橋駅にしてください』と駅名を統一するように要請はしていません。駅名に関して、先方から相談されたこともありません。また、逆に『汐見橋駅を桜川駅に改称してほしい』と打診されたこともありません」(同)
本来なら、後から駅を開設した大阪メトロと阪神が汐見橋駅を名乗るのが筋だろう。駅名の不統一は、乗客の利便性を損ねる。
微増傾向にあるとはいえ、汐見橋駅―岸里玉出駅間の利用者数はいまだ少ない。鉄道ファンからは廃線になってもおかしくないと囁かれているが、南海は汐見橋駅に不思議な期待感を抱いている。その背景には、なにわ筋線という巨大プロジェクトの存在がある。
なにわ筋線は、関西空港と大阪の繁華街・梅田方面を結ぶ新路線。2031年に開通を予定している。なにわ筋線の途中駅として汐見橋駅にも駅を設置する計画が立てられていた。なにわ筋線の汐見橋駅が誕生すれば、4路線が利用できる大阪ミナミのハブになる。当然ながら、汐見橋駅の利用者は急増するだろう。
先日、国土交通省はなにわ筋線の計画ルートを発表。汐見橋駅は、なにわ筋線の計画ルートから外れた。
それでも、南海の担当者は「国土交通省の案は、あくまでも予定。まだ、汐見橋駅が完全にダメと決まったわけではありません」と口にする。いまだ南海は未来への期待を絶やしていないのだ。
観光客でにぎわう高野山を尻目に、南海は汐見橋駅に期待を灯し続ける。都会の片隅で、高野線のターミナル・汐見橋駅はポツンと佇む。