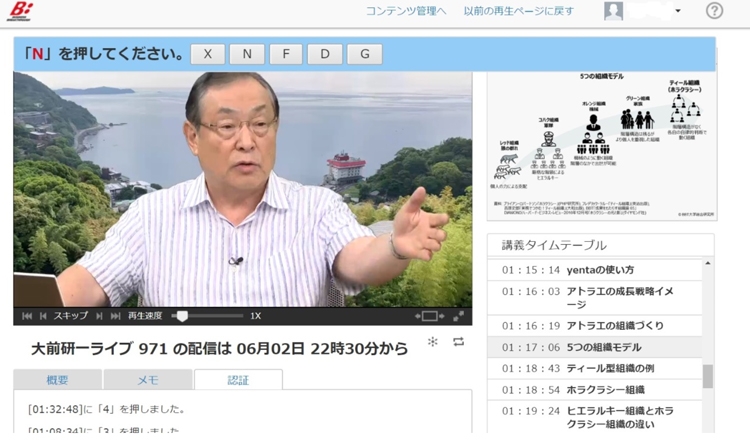オンラインでも集中力を途切れさせない仕組みを多用している
また、BBTの学生の7割は、パソコンではなく通勤時や昼休みなどにスマホで講義を視聴しているので、受講中のキーボード操作が難しい。そこで、スマホに搭載されている加速度センサーを利用して、前述の出欠確認記号が出てきたらスマホを振ればよいようにしたり、画面をタップしてもよいようにした。これらはすべて特許になっている。
さらに、学生同士のディスカッションで、相手の意見に賛成ならスマホを縦に、反対なら横に振るという技術も導入した。こういった仕組みは、企業がテレワークで社員に経営方針や日々の業務に対する指示を伝えて双方向のコミュニケーションを取る際に応用することもできるだろう。
あるいは、一人の教授が一方通行で講義をしていると途中で学生が退屈し、いくら出欠確認システムがあっても寝てしまうという問題があった。そこで、アシスタントとしてキャスターを起用し、教授に合いの手を入れたり、学生からの質問を読んだりするようにした。すると、学生は全く寝なくなった。いま日本の大学などは慌ててZoomなどを使ってオンライン授業を始めているが、大半は先生が後ろ姿で白板に向かっている。それではどうしても学生の集中力が続かない。
つまり、オンライン授業やテレワークは、従来とは全く違う発想とルール、仕掛けでやらねばならない、ということである。たとえば、BBTのエアキャンパスのクラスでは、1週間1テーマでディスカッションを行なっている。そこでの発言は必ず根拠を明示するルールだ。そのため、パワーポイントや写真、分析グラフなどの資料を添付できるようになっている。