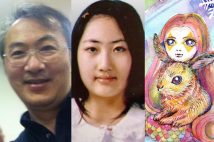席の間隔をあけてほぼ2ヶ月遅れの入学式(時事通信フォト)
永坂さんの手取りは25万円ほど、年収換算で400万円程度と平均よりもやや高く、公務員ということで絶対的な安定感もあった。その上夢だった教職に就いていることを考えれば、多忙さは仕方がないことと自分に言い聞かせてきたという。
「2ヶ月遅れで新学期が始まりましたが、授業も短縮で、行事やクラブ活動もほとんどありませんから、残業をしたり休日出勤はまずない。親御さんたちは、お子さんの学習が遅れや運動不足などの懸念があるでしょうし、一刻も早く以前通りの生活を望まれているんでしょう。しかしそうなると、我々はまたプライベートのほとんどない、以前の生活に後戻りすることになる」(永坂さん)
後戻りをしたくないというのが永坂さんの本音ではあるが、学校長や教育委員会、文部科学省が「以前と同じように戻す」と決めてしまえば、その時はたぶん従ってしまうだろう。だが、いったん気づいてしまった人間らしい生活は諦められなくなって、ひょっとしたら教師という仕事へのやりがいという、根本的なところへ疑問を持ってしまわないかと不安だ。
今求められている「新しい生活様式」は、何も新型コロナウイルスに感染しないためのライフスタイルのみを指すわけではないのではないか。埼玉県在住のベテラン中学校教師・佐々木典子さん(仮名・40代)は言う。
「激務でも、教員は聖職者という向きが強く、さらに公務員ですから、子供たちの成長や教育に全てを捧げるのが当たり前、という風潮がありました。今回、コロナのおかげで教員の中にも、今までのままでいいのか、とふと立ち止まって考え直すようになった人は少なくない。私もその一人です」(佐々木さん)
佐々木さんによれば、親たちの中でも意見は割れている。一刻も早く、以前と同様の学校生活を求める声もあれば、学校での学習やスポーツの時間を減らし、子供たちに伸び伸びと好きなことをさせたいという希望を口にする親もいると言う。
「入学式や卒業式などの外せないイベントを除けば、毎週土日のクラブ活動や、PTA活動などの学校行事がなくなり、本当によかったという親御さんもいらっしゃいます。学校が始まり、こうした価値観の違う親たちの対立も目立ち始めています」(佐々木さん)
対立しているのは保護者たちだけではない。教員たちも実は、新型コロナウイルスへの向き合い方は様々なので、まとまっていないのが実情だ。これからは、以前とまったく同じように学校生活を送ることは難しいだろうと考える教員もいれば、とにかく元通りにするのを優先すべきという教員もいる。いったい、これから学校は子どもたちの生活の場として、職場としてどうなっていくのか、不安だけが共通している。佐々木さん自身も、これからどう子どもたちと向き合い、仕事をすすめるべきかを決めかねている。
政府は、学校の「9月入学」について、この1~2年での導入を見送ると表明している。しかし単に時期だけの話ではなく、そもそも学校教育とは何か、教員とはどうあるべきか、という根本の考え方に想いを馳せることも「新しい生活様式」の重要な部分かもしれない。