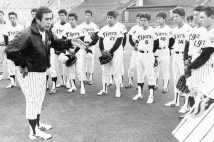『冠婚葬祭入門』の著者・塩月弥栄子氏は今の日本を見たらどう思うか?
もちろん、出版から50年が経ち、制度変更などがあったために参考にならない項目もあるが、その一方で現代にまで通底する項目も数多くある。たとえば、次のような記述がそうだろう。
〈祭壇には故人が気に入っていた写真を飾るとよい/きまじめで、面白味のないものより、故人が生前気に入っていた自然のままの笑顔の写真のほうがよいと思います〉
令和の時代の“見送り方”に葬儀・お墓・終活コンサルタントの吉川美津子氏は同様の指摘をしている。
「遺影を選ぶ過程は、家族で故人を偲ぶ時間を共有するという大事な意味があります。お金をかけなくても心のこもったことができるのが、遺影選びなのです」
他にも、〈葬儀社へは予算をはっきり言っておく〉といった項目は現代においてもトラブル回避のために必須といえるだろう。
同書には、葬儀に参列する側のマナーやしきたりについても解説されている。
〈とりあえずの弔問は、平服のままでよい/突然の死に接した遺族は、故人のふだんからの知り合いに電話でその悲しみを伝えてきます。そのようなとりあえずの弔問にいくときは、平服のままかけつけます。(中略)礼装の弔問では、遺族に不幸を予期していたととられることにもなりかねません〉
コロナ禍では“とりあえず駆けつける”という場面は少なくなるかもしれないが、ここで塩月氏が伝えようとしたことの本質は変わらないだろう。「遺族がどう感じるか」を考えて葬儀に参列する必要があるということだ。
〈故人との対面は、自分から言い出さない/よほどの間柄でない限り、自分のほうから「拝ませてください。」とは言い出さないことです〉
〈遺族に故人の死にいたる過程をたずねないほうがよい/弔問客は、自分と遺族とを、一対一と考えないで、遺族をつかれさせない心づかいが必要です〉といった項目からも、そのことが読み取れる。