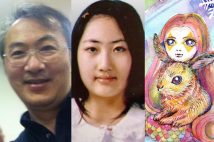風力発電の風車(イメージ)
こうした環境対策を講じながらも、鉄道業界はCO2の排出を削減余地が残っているとして、今後も環境対策を進めようとしている。
昨今、官公庁舎や建設業界では環境意識の高まりから、環境負荷の少ないZEB(Net Zero Energy Building=ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング)やZEH(Net Zero Energy house=ネット・ゼロ・エネルギーハウス、)が推進されるようになってきた。
ZEBやZEHは、消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のこと。ゼブやゼッチと読み、一般的に耳にする機会は少ないが、官公庁や建設業界ではお馴染みの用語になっている。
環境負荷を低減させるZEBやZEHといった取り組みは今後も進んでいく潮流にあるが、黎明期の今はZEBやZEHは建設費や維持費によって割高になる。また、工期が長くなるといったデメリットがある。
こうしたデメリットは技術開発とともに薄れていくだろうが、現段階ではデメリットの方が大きい。それらを覚悟してまでZEBやZEHに取り組もうとする事業者は多くない。だからこそ、行政が補助金などの優遇措置を設けて旗振り役になっているわけだが、それでも社会全体に普及するには時間を要するだろう。
そんな中、鉄道事業者が駅舎・線路用地といった固定資産の有効的な活用に動き出した。前述したZEBやZEHのように、環境に配慮した駅をつくる試みはゼロエネルギーの駅をつくろうという試みだ。それらはZES(Net Zero Energy Station=ネット・ゼロ・エネルギーステーション)と呼ばれる。
◆電力事業と鉄道会社
ZES化を進めているのは、東京メトロだけではない。JR東日本は2014年に京葉線の車両センター内にメガソーラー施設を建設。2015年には常磐線にもソーラーパネルを設置し、2017年には福島県富岡町の復興支援の一環として富岡復興メガソーラー・SAKURAの運転を開始。
駅舎で取り組まれている再生可能エネルギーの利活用は、太陽光発電だけにとどまらない。列車が走ることによって自然と風が生まれることをうまく利用し、駅ホームや線路沿いに風力発電設備を設置している。
東京駅と蘇我駅を結ぶ京葉線は、路線の大半が海沿いを走っている。そのため、海風の影響を大きく受け、利用者や鉄道ファンの間では強風ですぐにダイヤが乱れる路線として知られる。そうした負の部分を逆利用し、京葉線の駅や線路では風力発電の設備を設置している。
鉄道会社が再生可能エネルギーの導入に取り組む背景には、停電などアクシデントが起きた際のリスクヘッジという側面もある。言うまでもなく、電車は電気を動力にしているので、停電が起きてしまうと電車がストップする。電車がストップしてしまえば、鉄道会社内だけの問題にとどまらず、社会全体に大きな混乱をもたらす。混乱を少しでも緩和する狙いが含まれている。