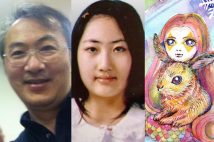「僕が彼らを『勝たせてあげなければならない』という気持ちが強すぎたのかもしれない。僕自身がもっと練習から身を入れるべきでした」とも上村監督は語った(写真は聖隷クリストファーのナインら)
最後は欲が出た
浜松商業や掛川西を率いていた頃にあったような、吐く息すべてに籠もった悔しさではなく、ため息交じりの悔しさが襲っていた。
「もしかしたら、無欲で戦ってきた彼らが、あと2勝で甲子園となって初めて欲が出てしまったのかもしれませんね。監督である僕が彼らを『勝たせてあげなければならない』という気持ちが強すぎたのかもしれない。僕自身がもっと練習から身を入れるべきでした。監督として失格です」
準決勝を3失点完投した今久留主は2年生で来年もある。打線でブレーキとなった4番の山崎や三塁手の堀内謙吾も2年生だ。彼らを鍛え直して、もう一度、甲子園を未来に描こうとは思わないのだろうか。改めて、私は上村監督が「退任」を視野に入れている気がしてならなかった。
日本高野連は静岡大会の期間中だった7月12日に、選抜の選考基準を明文化した「選考ガイドライン」を公表した。だが、今春の騒動を受けた改革は何もなく、「選抜高校野球大会は招待試合」「本大会の特色は予選を持たないこと」「勝敗のみにとらわれず、出場にふさわしい学校を選出する」などと、むしろ「聖隷落選」の選考を正当化するかのような内容だった。
当然、上村監督をはじめ聖隷の関係者もこの不愉快なガイドラインを目にしていたことだろう。聖隷にとって、聖隷こそ選抜出場校に相応しかったという自らの「正当性」を訴える唯一の手段が、夏の静岡大会を勝ち抜き、甲子園出場を果たすことだった。しかし、あと2勝というところまできて、道は潰えた。
そして、この現実に、誰よりも悔恨と落胆を抱えているのが上村監督であり、敗戦のあと、数時間が経過しても上村監督の心は揺れていた。夏の快進撃をみせた選手を讃えたかと思えば、甲子園にたどり着くには力がなかったと偽らざる本心を吐露する。球児にとって唯一無二の夢である甲子園出場を奪った大人たちへの恨み節も包み隠さず明かし、同じ大人として教え子を勝利に、甲子園に導いてあげられなかった責任をひとり痛感している。
春、失意にくれたナインを甲子園から脇道にそれた路頭に迷わすわけにはいかない――その一心で65歳の身体に鞭打って上村監督は灼熱のグラウンドに立ち続けた。私は春からの付き合いの中で、上村監督や聖隷のナインに対して軽々しく「選抜落選の悔しさは夏に晴らすしかない」とは口にできなかった。だが、今は――。
この春と夏の悔しさは、甲子園出場を果たすことでしか晴らすことはできないだろう。もちろん、そのチームを率いるのは上村監督である。この物語を、聖隷クリストファーの悲劇ではなく、聖隷クリストファーの奇跡として終わらせることが、高校野球を引退した3年生への手向けとなるのではないか。
(了。第1回から読む)
【著者プロフィール】柳川悠二(やながわ・ゆうじ)/1976年、宮崎県生まれ。2016年に『永遠のPL学園』で第23回小学館ノンフィクション大賞を受賞。新著『甲子園と令和の怪物』(小学館新書)では、ロッテ・佐々木朗希の大船渡高校時代の岩手大会決勝「登板回避」について、当時の國保陽平監督の独占証言をもとに詳細にレポートしている。