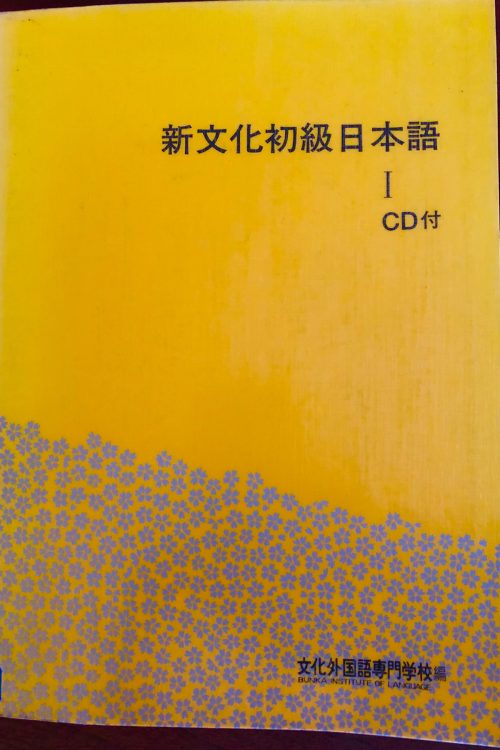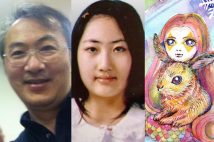ラウラさんが日本語学習で使っていたテキスト
そういう教え方は初めて聞いた。テキストを使用しても、文法を1から教えるわけではないというのはすごく新鮮に感じる。
「一部の授業を免除してもらっていた分だけ、頑張って勉強しなければと思っていたので、図書館で毎日集中して先生の日本語を聞いている頭の中で、きっとものすごい変化があったと思うんです。その変化があらわれたのは2か月後くらいでしたね。あ、日本語話せる! と気付いたんです。
フィンランド語で、裏技がない、とにかくやるしかない勉強のことを『座る筋肉が必要な勉強』って言うんですけど、まさにそんな感じ。英語は絶対に使わず、聞くものも見るものも全部日本語。私、ストイックなところがあるので、そういう逃げ場のない状況に置かれたのが合っていたのかもしれません。
あと、今、振り返って思うのは、子供であるとも言える年齢の高校生の頃に留学できてよかったなということです。大人になると、やはり仕事をしなければなりませんから、勉強に専心することはなかなか難しい。でも、子供は学ぶのが仕事。言語はツールで、学びの対象、ゴールでもあるので、いいタイミング、いい学習環境で勉強できてよかったと思っています」
「手加減」をされるのが一番堪える
1年間の留学を経てフィンランドに帰国後、ヘルシンキ大学在学中に交換留学で早稲田大学へ。その後北海道大学大学院を修了。申し分のないプロフィールに「ラウラさんのような方は、もしかしたら言語獲得に苦労はしなかったんじゃないだろうか……」と、お話を伺いながら思ってしまった。何か大変だったことはあったのだろうか。
「日本語は、文法の理解と文化的な理解がセットになって初めて『話せる・使える』って言えるんだと思います。文法的に間違っていなくても、言いたいことがその場に相応しいか、どんな表現を使うのが適切なのか分かっていないと『生活者』としてつらいんですよね。たとえば英語だと、相手の言葉を聞いて『あ、いいね』と思ったら試しに使ってみることができる。でも、日本は関係の上下によって言葉遣いが違うからむやみに真似できない。男性と女性でも微妙に違うし、漫画の言葉遣いは現実では使わないほうがいいこともあるし。
友達とは対等だから……と思っても、失礼にならないか心配になって『です・ます』で話すと『かたいよ』って笑われてしまったりね。隣に住んでいたアメリカ人にも似たような話を聞いたことがあるんですけど、やっぱり怖くなっちゃうんです。
メールも難しい。会話とはまた違った神経を使う面があると思います。対面で話している時に表情と言葉がマッチしていなかったら『あ、この人はまったく悪気はなくて、使い方を間違っているだけなんだな』と分かるけど、文字だけだと結構誤解されやすい。丁寧に書かなきゃ、と思って書いたら、冷たい印象を与えてしまったらしいと感じたことも結構ありますね」
誤解、冷たい印象、齟齬。コミュニケーションは避けがたくそれらを包含してしまうものだ。ラウラさんがおっしゃるように、文化の違いが根幹にあることも少なくないだろう。