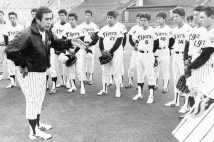謝罪をしても釈明をしても「キャンセル」に至らないと騒動が収まらないことが増えている(イメージ)
「飲料メーカーの伊藤園さんが、AIの女性を広告に採用したことが話題になりましたが、当初クライアントの反応は冷ややかでした。いくらなんでもAIはない、まだアニメキャラの方がマシだと。広告に起用するタレントのイメージが商品のイメージを押し上げるのですから、人格が全くないAIを起用しても意味がない、という見方でした」(牧野さん)
しかし、続々と判明する芸能著名人のスキャンダルを前に、クライアント側の意識も変わりつつあるのだ。
「テレビだけではありません。映画や雑誌、ポスターに至るまで、形として残るものは、出演していたタレントの後の言動や、掘り起こされた過去によって“無かった事”にされかねない。そういったリスクを背負わなければならないなら、AIでもいいじゃないかと」(牧野さん)
AIキャラクターが話題になる前は、アニメの主人公やキャラクターを起用した広告なら大丈夫だろうと採用が増えた時期もあった。ところが主人公役の声優にスキャンダルが出たり、キャラクターの運営会社に不祥事が出てしまい、やはり“キャンセル”の対象になり、案件が台無しになった例もあるという。
一方、クライアントやメディアを介さずに芸能人自身が運営する動画サイトやSNS、さらに新興のネットメディアでは事情が異なる。たとえ脛に傷がある芸能人であろうと、積極的に起用しようという動きが目立つのだ。
「既存メディアは、とにかくコンプラを理由にした縛りが厳しく、自分で自分の首を絞めている感さえあります。その辺りが緩いネットメディアだと、うるさいクライアントからの注文もなく、不祥事自体をネタにしてコンテンツが作られる傾向が強く、人気を博しています」(牧野さん)
“キャンセルカルチャー”の拡大により、芸能人やタレントたちには、かつてないほど、極度の清廉性が求められつつある。事件や事故を起こして明確に責任を問われる段階ならまだしも、「疑惑」が出た瞬間に長く積み上げてきたものを全て否定するような勢いだ。疑いが晴れたり、罪を償ったあとでも、表舞台に戻るのが難しい時代になってしまった。
このままいけば、もはや既存のメディアから“キャンセル”の可能性がある血の通った人間の姿は、綺麗さっぱり消えてしまうのかもしれない。