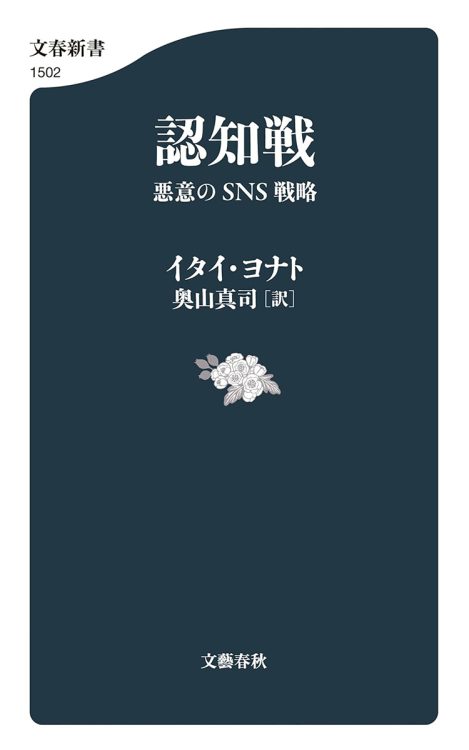『認知戦 悪意のSNS戦略』/イタイ・ヨナト・著 奥山真司・訳
【書評】『認知戦 悪意のSNS戦略』/イタイ・ヨナト・著 奥山真司・訳/文春新書/990円
【評者】辻田真佐憲(近現代史研究者)
これまでプロパガンダの多くは失敗してきた。それにもかかわらず、その効果が必要以上に喧伝されてきた。歴史家はこの事情をよく知っており、プロパガンダの過大評価に警戒的だ。そのいっぽうで、現代の情報化社会に軸足をおく論者は、認知戦や影響力工作といったことばで、その危険性を強調する傾向がある。評者は前者に属し、本書の著者は後者に属する。そこであえて本書を手に取った。
著者はイスラエル軍で諜報部員として活躍したのち、インテリジェンス企業を創業した人物。類書と異なり、認知戦のカウンターに関わっている実務者だという点が特徴的だ。そのため、内容はきわめて具体的。どのようにSNSのハッシュタグを使えば偽情報に対抗できるかまで言及されている。そもそも中国やロシアが日本で認知戦を展開していることも一般にはあまり指摘されておらず、その点ではきわめて啓蒙的な内容といえる。
だが、気になる点もある。著者は「イスラエルが罪のないパレスチナの人々を殺している」という批判を不当なものとみなし、ハマスとイランによる認知戦の影響を指摘している。
われわれは「この情報は某国の工作だ」と言われるとハッとする。だが、その主張自体が認知戦となりうる危険もあるのではないか。また仮に何らかの工作が行われていたとしても、それが残虐行為の存在をかならずしも否定することにはならない。
ひとはだれでも利害関係を抱える。卑近な例だが、認知戦を強調すれば関係する役所や大学で予算が確保され、世論工作会社には仕事が増える。このような事情も踏まえつつ、われわれは中国やロシアの認知戦にも向き合わなければならない。世界のどこにも真っ白な情報はなく、灰色のなかで試行錯誤するほかない。本書は、今日の認知戦をめぐる言説の厄介さについても教えてくれる。
※週刊ポスト2025年10月3日号