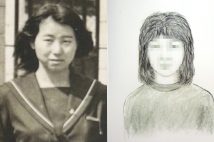各地でクマの被害が相次いでいる
東北・北海道を中心に、熊被害が相次いでいる。人々が震えるのは、山中どころか、市街地で襲われるケースが多発していることだ。そもそも熊は「狩りが苦手」で「主食は木の実や樹木、肉食は魚や昆虫が基本」だという生態がある。なのになぜ、人里に近づくようになったか。
近現代の熊被害をまとめた別冊宝島編集部編『アーバン熊の脅威』では、市街地に現れる“アーバン熊”誕生の背景を分析。それによれば、昭和時代、一度は絶滅寸前まで追いやられた熊をはじめとした野生動物は、その後の「熊撃ち禁止令」やハンターの減少などで増加。並行して農作物への食害を及ぼすシカやイノシシを捕まえる「罠猟」を仕掛けたところ、若熊たちがその罠にかかった動物を食べることを覚えたのだという。
そして肉の味を知った熊たちは、住宅地近辺の里山にやってきて、ついには「山を捨てる」ようになった。その経緯を同書より一部抜粋、再構成して紹介する。【前後編の後編。前編から読む】
* * *
熊の寿命は生存環境によるが、20年から30年とされている。
絶滅寸前まで追い詰められた旧世代の「昭和熊」は人間を恐れ、人里を“恐ろしい場所”と認識していた。農作物や家畜を食べたことはなく、その“味”を知らなかったはずだ。
だが1989年に熊狩りが禁止となり、熊保護が叫ばれてきた平成期に生まれた熊は、人間を“恐ろしい存在”として認識しなくなった。たとえ人里に降りても殺されずに山へと戻されるだけなのだ。恐れることはない、むしろ人間を次第にナメていったことだろう。人里近い果樹園や農地へと進出した「平成熊」は農作物の“美味しさ”に気づく。また、罠にかかった害獣を食べて肉食化していた熊のなかには、家畜の味を覚えた個体も増えたことだろう。
熊は1年半から2年かけて小熊の子育てをする。平成生まれの熊たちは「人間を恐れる必要はない」「罠にかかった獲物は横取りできる」「人里近い果樹園や農地で農作物を食べることができる」といった新たに獲得した特性を小熊に教えていったはずだ。
この平成熊から生まれた新世代の熊たちが「アーバン熊=令和熊」となっていくのだ。
アーバン熊=令和熊の最大の特性は、「山を捨てた世代」という点にある。
たしかに放棄された荒廃山林や里山は野生動物の楽園となった。だが、そこで生きていける数には限度がある。生息数が増えれば、当然、過酷な生存競争が発生する。しかも激増したシカやイノシシとも食糧をめぐって争っているのだ。
ドングリ類など食糧の豊富な環境域である荒廃山林や放棄里山は、「熊の楽園時代=平成期」には、経験と肉体を大きく成長させた“成体”の熊が独占してきた。だから平成熊は山を降りる必然性はなかった。しかし令和期に入って生まれた若熊たちは違う。老練な平成熊との競争にさらされる山では“生きていけない”のだ。