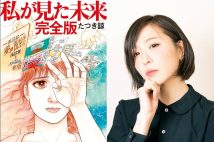生育時期や形、大きさなどが不揃いで、今の流通に乗ることが難しい「固定種・在来種」
2016年秋、恵泉女学園大学教授の藤田智さんが「1980年には1214種あった日本の伝統野菜が、2002年には556種以上へと減少した」と発表し、話題を呼んだ。今、絶滅の危機にある日本の伝統野菜を守ろうと活動している八百屋・warmerwarmerの高橋一也さんに話を聞いた。
日本にはその土地に根ざしたたくさんの野菜があり、分類上はただの“大根”でも、その土地ごとの大根があって、実に個性豊かだと高橋さんはいう。例えば大根なら、宮崎県椎葉村の人々が800年も前から栽培してきた「平家大根」や、長崎県平戸市で室町時代から栽培されている「木引かぶ」など。
古来種野菜というのは、高橋さんが付けた野菜の呼び名で、日本各地に昔から存在していた固定種や在来種と呼ばれる伝統的な野菜の総称だ。
これらの野菜はいきなり食べられる形になるわけではなく、種からスタートする。野菜の種はあまり知られていないが、小さな種が土に蒔かれて、芽を出し、土の養分と水や太陽の恵みを受けて育って、食べられるまでになる。
それだけに種がとても大切であり、平家大根も木引かぶも、何百年とその種を伝えてきた人がいるから、今日まで残っているのである。しかし、ここ30~40年ほどの間に400種もが絶えてしまったといわれるように、農業に従事する人の高齢化、農村の過疎化などによって、どんどん減っているのは事実なのだ。
ところで、野菜の種は、「固定種・在来種」と「F1種」に分けられる。
「固定種・在来種というのは、農家さんが野菜の種を採り、その種を蒔いて育てて、また種を採る。この作業を繰り返して得られた種です。固定した形質が親から子へと受け継がれていくのが特徴です」(高橋さん、以下「」内同)
これは残念ながら今、市場に出回る量は極めて少なく、絶滅危惧種が多い。なぜなら、不揃い、不安定、生産性が低い、非効率的な野菜だからだ。