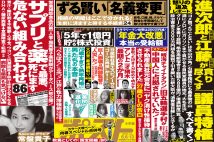『「首尾一貫感覚」で心を強くする』の著者、舟木彩乃氏
◆こんな職場も「ブラック」
たとえば、上司の言うことがコロコロ変わってしまうと、部下は何を優先すればいいのかわからなくなってしまう。営業を担当する社員に向かって「とにかく売り上げを上げろ」と言ったかと思えば、「安売りするな」と怒鳴ったり、「拙速でいいから早く結果を出せ」と言う一方で、「ミスするな。慎重にやれ」と注意してきたり……。上司の意図が把握できないと、部下の「把握可能感」は低くなり、「だいたいわかった」と思えなくなる。
「どこに“地雷”があるかわからない、いつキレるか予測できない上司は、部下にとっては本当にやっかいな存在です。機嫌の良い時と悪い時で対応が変わったり、言っていることとやっていることに差がありすぎたりといった状態が続くと、その下で働いている社員たちは今後の展開が予測できずに、ストレスが溜まっていきます。
また、書き入れ時や決算期などに多忙を極める職種もありますが、期限が決まっていると、把握可能感が高まるのでストレスを抑えることもできます。ところが、忙しい時期がいつまで続くかわからないとなると、社員はますます疲弊してしまいます」
2つめの「処理可能感」は、目の前の問題も「なんとかなる」「なるようになる」と感じられる感覚。これは、職場の人間関係によっても左右されるという。
「厳しいノルマが課せられたり、とても処理しきれない量の仕事を押しつけられたりした場合、『なんとかなる』とは思えなくなり、『処理可能感』を持てなくなります。人手不足なのにその手当てもせず、さらに業績を上げようとする上司の下では、そのしわ寄せは社員一人一人にまわってきます。
そんな時でも、同じ職場の先輩や同僚がサポートしてくれたり、アドバイスしてくれたりすれば処理可能感は高まります。しかし、他の社員を助ける精神的な余裕がない職場では、一人で仕事を抱えてしまうことになります。そうした職場は、たとえ上司が直接、パワハラをしたわけでなくても、ブラックだと判断すべきでしょう」
「モンスタークレーマー」と呼ばれるような無理難題をふっかけてくる顧客も、何を言いだすかわからず、まっとうな対応をしても聞く耳を持っていないといった点で、「把握可能感」や「処理可能感」を脅かす存在だと言えるだろう。
◆「追い出し部屋」との共通点
さらに、どんなに大変な仕事でも、そこに「意味」を見いだすことができれば、過剰なストレスにも耐えることができる。それが、首尾一貫感覚の3つめの「有意味感」であり、「この壁は乗り越えるべき価値がある」とか、「この仕事を成し遂げれば、多くのお客様の役に立てる」と意味づけできれば、より大きな成果を上げる原動力にもなる。