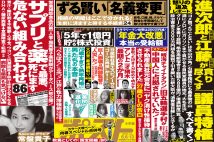日本史との関係でいえば、歴史書の『三国志』は日本について言及した最古の文献史料でもある。『三国志』は「魏書」「呉署」「蜀書」の三部からなるが、その「魏書」の中の「東夷伝」の中に倭国、すなわち日本について触れた部分があるのだ。俗に「魏志倭人伝」と呼ばれ、日本の歴史書には登場しない邪馬台国と卑弥呼の名が初めて登場するのもその部分である。
卑弥呼が魏の都に最初の使節を送り出したのは238年のことで、魏からも答礼の使節が倭国を訪れていることから、「魏志倭人伝」の記述はその使節の報告書をもとに記されたと考えてよい。
だが、そこに問題がないわけではない。双方の言語を操る通訳がいたとは思えず、日本側がいまだ無文字社会であれば筆談もできない。いったいどうやって意思の疎通や細かなやりとり、情報の収集が行なわれたのかが謎のままなのである。
一つ考えられるのは中国語と朝鮮語の両方を操れる者、および朝鮮語と日本語の両方を操れる者が同行。二重通訳によりコミュニケーションが図られた可能性である。これであれば倭国に関して詳しく記されているのも納得がいく。
今回の三国志展では卑弥呼と同時代の文物が数多く展示されるので、『三国志演義』のストーリーやひいきの登場人物に熱を上げるもよし、三国志の動乱に遠く日本も関わっていたことに思いを馳せるのもまた一興であろう。
【プロフィール】しまざき・すすむ/1963年、東京生まれ。歴史作家。立教大学文学部史学科卒。旅行代理店勤務、歴史雑誌の編集を経て現在は作家として活動している。著書に『ざんねんな日本史』(小学館新書)、『春秋戦国の英傑たち』(双葉社)、『眠れなくなるほど面白い 図解 孫子の兵法』(日本文芸社)、『いっきにわかる! 世界史のミカタ』(辰巳出版)、『いっきに読める史記』(PHPエディターズ・グループ)など多数。