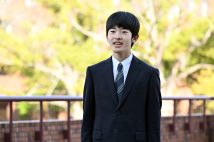在庫過剰の商習慣はリセットできない
今回のコロナショックでアパレル業界の苦戦が深刻化しましたが、報道などでは「これを機に在庫を多く抱える供給過剰の商慣習を見直すべき」という論調も多く見受けられます。基本的には賛成ですが、何十年と続いてきた商慣習をいきなりリセットするわけにはいきません。それこそ多くの倒産企業が生まれ、失業者が急増するでしょう。
物販で生計を立てていない人には実感がわかないかと思いますが、物販では100億円の売上高を稼ごうとするなら100億円分の在庫量が必要になります。50億円分の在庫量しかなければ完売しても売上高は50億円にしかならないのです。
資本主義経済における企業の目的とは成長することですから、これまでずっと前年実績を上回る売上高が目標に掲げられてきたのです。そして、それに比例して用意する商品量も増え続けてきたというのがアパレル業界の構造です。
そして、在庫量が増えたからといって、一律に新規の仕入れ量や生産量を減らせば、売上高が確実に下がるばかりか、下手をすると営業利益(本業による儲け)も減りかねません。
洋服の仕入れや生産量を減らせば販売の機会損失が起きる恐れも
基本的に多くのアパレル店舗はトータルアイテムを販売しています。Tシャツだけジーンズだけワイシャツだけという単品販売の店は多くありません。ジャケット、ズボン、シャツ、Tシャツ、セーターという具合にトータルアイテムを販売しています。そして、それぞれ数種類の色・柄があります。それを一律削減してしまえば、本来なら売れ筋になる品番も減らすことになり、販売の機会損失が起きてしまいます。
ですから、アパレルが新規の仕入れ品や商品製造を削減するにしても、「Aという商品はまったく減らさないが、Bという商品は7割減らす」というような自店舗・自ブランドの特性と照らし合わせた分析が必要となるのです。
この分析は方程式のように決まったロジックが存在するわけではありません。なぜなら、売れ筋・死に筋はブランドごとにまったく異なるからです。要するに、供給量を削減するためには各社・各ブランドそれぞれでの精緻な分析が必要となり、その分析の精度を上げることが唯一の正解なのです。
来年春からの倒産ラッシュを現実化させないためにも、各ブランドは自社の置かれた経営実態を正確に踏まえたうえで、早期の売り上げ回復に努めていただくことを切に願っています。