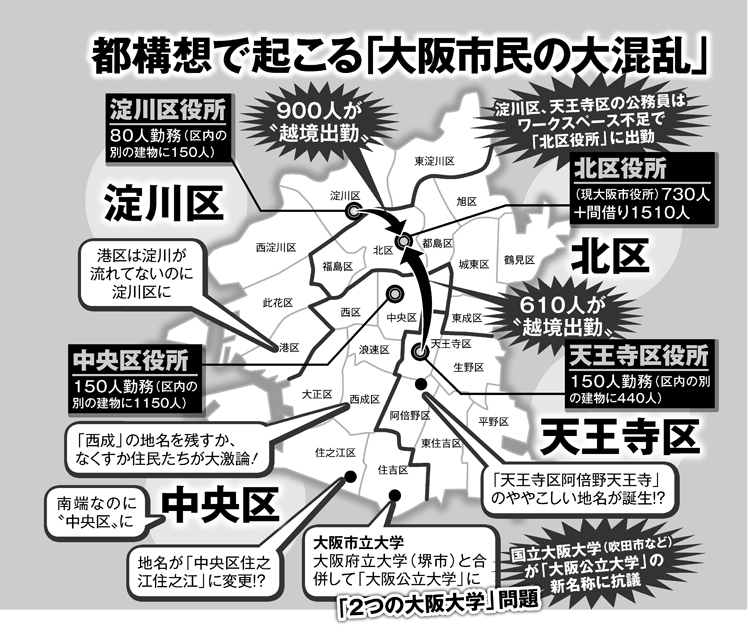都構想で起こる「大阪市民の大混乱」
大阪市所管の行政サービスが特別区に4分割されるものは他にもある。「保健所」や「図書館」も特別区ごとに運営されることになる。行政に詳しい高寄昇三・甲南大学名誉教授が指摘する。
「市内最大の中央図書館がある新・中央区の蔵書冊数だけ飛び抜けて多くなります。高齢世帯の多い特別区では予算の増大が懸念され、保健所などの業務の実施状況に格差が生じる可能性もある」
こうした反対派の主張に対して真っ向から反論するのが、賛成派の大阪維新の会だ。大阪維新の会・都構想戦略本部事務局長の横山英幸府議はこう語る。
「スケールメリットは、スケールデメリットと両論で議論すべきです。大阪市のままでは一律の行政サービスになりますが、4特別区にすることで高齢世帯の多い区は高齢者政策を重視し、子育て世代の多い区は教育費を助成するなど、無駄なく効率的な住民サービスが提供できるようになります。
財政悪化についても、住民投票で問われる『協定書』の中身で議論すべきです。特別区が負担する初期投資204億円は大阪府から財政措置がある。また14億円のランニングコストにも17億円の財政調整があるため、実質的な市民の負担はゼロなんです。こうした事実に目をむけていただきたい」
大阪市内では現在、賛成派と反対派が激しい舌戦を繰り広げている。住民説明会の会場前には、反対派がプラカードを掲げて主張する場面も見られた。住民サービスが良くなるのか悪くなるのか―市民生活に直結する問題だけに、丁寧な説明が求められることは言うまでもない。
●取材/竹村元一郎(ジャーナリスト)
※週刊ポスト2020年10月16・23日号