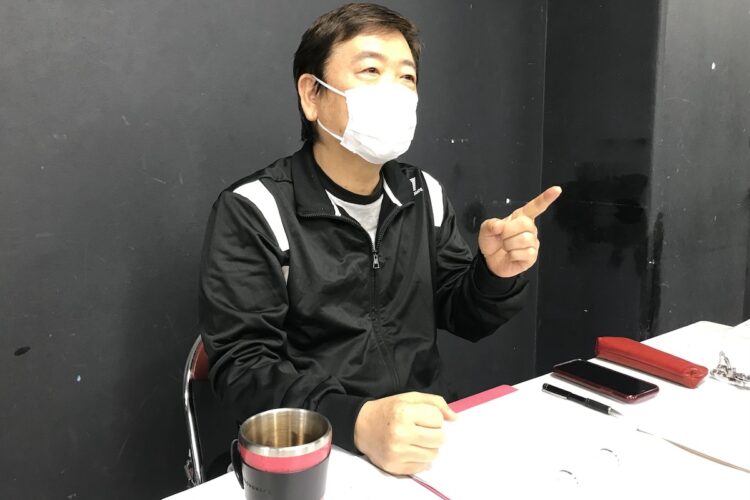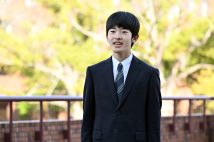感染症対策を徹底し、新作舞台の稽古に励んでいる(サードステージ提供)
僕の場合は、「分をわきまえろ」とか「周囲と合わせろ」といった世間の同調圧力に長年抵抗してきたタイプ。だから、新人の皆さんに同じような態度を取ることは決してオススメはしません。だけど、〈世間だけじゃなく、社会の視点からものを見る〉ことがとても大事なんだということは、皆さんに知っておいてほしいのです。
〈社会の視点〉をもつために
「世間」とは自分に関係のある人たちだけで形成される世界のこと。学校や会社、隣近所といった身近な人たちでできている世界です。一方、「社会」とは自分と関係ない人たち、たとえば同じ電車に乗り合わせた人とか、映画館で隣に座った人など知らない人たちで形成されている世界のことです。
同じ世間に生きていても同調圧力をプレッシャーとして感じやすい人とそうでない人がいます。その違いは、社会の意識を持っているかどうかです。僕の場合、演劇サークルという世間にとどまっているのではなく、観客を増やすというふうに社会のほうに目を向けていきました。「先輩に認められなくたって、観客を増やしていけばいいんだ」と思えたからへこたれませんでした。
社会の視点をもって、社会とつながり、「社会話(ばなし)」ができるようになるといい。世間話は「おでかけですか?」「ちょっとそこまで」というような、「同じ世間に住んでいますね」という確認の会話のこと。
社会話は、たとえば3.11の後に余震が起こったときに「いま揺れましたね」「こわかったですね」と道ですれ違っただけの人に話しかけるみたいなことです。それだけでもすごく気分は落ち着くものです。
お店に行って天気の話をしたり、「美味しかったです」と言ったりするのも、たわいない話のようだけど実はお互いにメンタルのケアをしているのです。これが社会をもつということ。「いきなり見ず知らずの人と話すのはハードルが高い」と感じるかもしれないけれど、そういう場合に、社会を手軽に見つける方法は「本を読むこと」です。