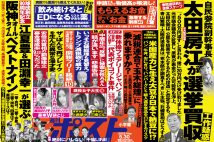西洋音楽の発信のため造られた初代の野音。写真提供/日比谷公園大音楽堂管理事務所
最初の危機は関東大震災だった
東京市民に新たな文化を発信すべく誕生した野音だが、すぐに危機的な状況を迎える。
「野音ができた2か月後の9月1日に関東大震災が起きました。数々の建物が崩壊し、日比谷周辺の建物や公園内の小音楽堂は倒壊しましたが、野音だけは無事だったんです」
未曽有の災害を奇跡的に免れた野音は、当時の東京市民にとって特別な存在になっていく。
「過去の記録によると、震災で落ち込んだ東京全体を元気づけるために、さまざまなイベントが行われました」
関東大震災以降も吹奏楽やクラシックコンサートが中心だったという記録も残っている。
「陸軍などの軍楽隊のコンサートが主だったようです。いまでも吹奏楽は屋外で演奏する機会が多いかと思いますが、太平洋戦争が始まる前までは陸軍、海軍の軍楽隊によるブラスバンドの演奏が行われ、観客を多く集めていました。
変わったところでは、ボクシングの試合などをする機会もあったようです。現在の収容人数は3000人程度ですが、初代野音の、1940年代くらいまでは消防法による制限はなく、5000〜1万人程度が集まっていたようです。いまみたいにロックや歌謡曲なんてない時代ですから、ボクシングも人気があり、人が集まるイベント会場として音楽以外のイベントも野音で行われていました」
1940年以降になると、時代のうねりに巻き込まれていく。
「1943年に太平洋戦争が開戦。西洋音楽の象徴的存在だったことから野音は休館せざるを得ない状況になりました」
幸い、東京大空襲の火の手からは免れたが、1945年に終戦を迎えるとGHQが接収。接収期間は6年近くになった。1954年、接収が解除されると野音は改修工事に着工。2代目野音が完成する。
「2代目ができた1950年代の日本は歌謡曲が大流行。海外からはロカビリー、フォーク、ロックなどあらゆるジャンルの音楽が輸入されるようになりました。その頃の野音では警視庁や、東京都消防庁の音楽隊の演奏や演劇、舞踏会などあらゆるジャンルのイベントが行われていたのです」
そして1960年代になると野音から新しい歴史が始まる。