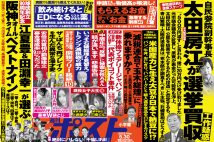2012年にJLPGAの競技委員となった門川恭子氏。1996年のプロテストに合格し、ステップアップツアーでの優勝経験もある元ツアープロでもある(筆者撮影)
質問は“どうしましたか?”から始める
「最初にやることは状況の把握です。競技委員が先入観を抱いて向かうとミスジャッジを招きます。プレー進行を滞らせないよう短時間で終わらせたいところですが、それでもあえて当事者の選手や同伴競技者には“どうしましたか?”の質問から入ります。
急がせてしまうと、プレーヤーは目の前にある状況だけを説明しがちです。そして判定を下した後になってから“(競技委員が来る前に)一度、球を拾い上げていた”なんて話が出てきたりする。状況を把握するためには、その状況に至った経緯を丁寧かつ正確に聞く必要があるのです」
最近のプレーヤーの特徴は、同伴競技者があまり関与してこないことにあるという。
かつては救済を受ける場合に〈マーカー立ち会いのもと〉という規則があったが、2019年のルール改訂でマーカーの立ち会いの規定はなくなった。
「したがって選手本人とそのキャディからの説明でジャッジすることになりますが、プレーヤーだけの情報では判断が不正確になってしまうことがあります」
そのような場合、正確に判断・決定するためにマーカーや同伴競技者、付近にいたギャラリー(観客)に訊ねるケースもある。
例えば砲台グリーンのホールでは選手たちからグリーン面は見えないので、先にショットした選手のボールに次の選手のボールが当たっても、選手やキャディにはわからない。2人ともグリーンに上がって初めて、ギャラリーから「2人目のボールが当たった」と知らされる。この場合は先に打たれたボールを“元にあった位置”に戻してプレーを再開するが、選手はその場所がわからないため、競技委員を呼ぶことになる。
「複数のギャラリーに聞き取りして確認したうえで、どのあたりに戻すかを判断しますが、結構大変です。“もっと近かったぞ”とか、“いや、それより遠かった”と意見が割れたりすることもあります」