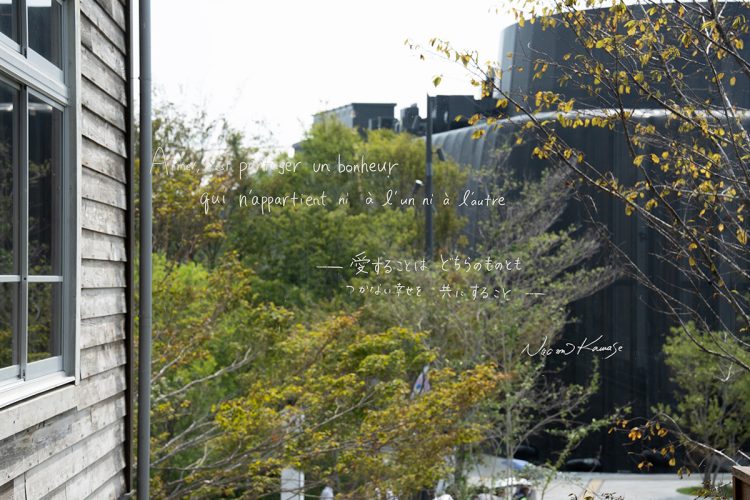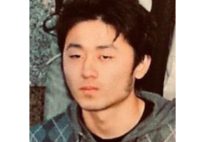「『対話によって救われた』とおっしゃる方もいて、こんなこともありました。
朝早くから並んでいたのに暑さや疲れからかイライラして喧嘩してしまってこのパビリオンに来た、という方。選ばれて語っていくうちに、自分もこうだったらよかったのに、ということを客観視しはじめ、泣きながら話していらっしゃいました。
またある回では、お母さんとあまりよい関係ではなかったという看護師さんが、『亡くなったお母さんへいま言いたいことはある?』と聞かれて、『産んでくれてありがとう』と答えていたのが感動的でした。この対話がなければ、その言葉がこの世に生まれることはなかったでしょう。
その時の対話の相手は、戦場カメラマン。戦地でコーディネーターが目の前で殺されてしまってトラウマを抱えているという方です。そして、看護師さんから『あなたは?』と聞かれて『僕の場合は・・・』と言いかけたところで10分がたちそこで終わってしまいました。『答えはない』ので、そこからはみなさんの感じたものを通して人生という物語を紡いでいってほしいのです」
河瀨直美さん自身が、シアターで挨拶に登壇することも
チャレンジだった“とれ高”がわからないパビリオン
こういったスタイルのパビリオンにするまでには、計画段階で反対意見もあったという。
「当然ですよね。老若男女にわかりやすいエンタテインメントではなく、『察してくださいね』という現代アートのようなパビリオンなので “とれ高”がわからない。来場者に渡していくものが担保できない、という中で、どういう形にすれば満足していただけるのか、5年ほどかけて考えてきました。全員がそれぞれ対話する、といった案も出たりしましたが結局、一対一の対話を皆が目撃するという形になりました」
作られた映像を流すだけではない、シナリオのないパビリオンというのはチャレンジだった。
「これは“河瀨映画”だなと思っています。もともと“河瀨映画”は、シナリオがあっても即興で俳優さんたちがセッションすることが多く、むしろそういったシーンのほうが作品のコアとなっている。それがこの対話でも起こって、ひとつの映画の形になっています。大きな賭でもありましたが、すごい可能性があると感じています」
ウクライナのキーウに住むカメラマンとつないで対話が行われた回もある。
「社会がいきなり変わるものではないけれど、私が伝えたいのは、戦争で武力行使する前に対話で世界を変えられるのでは、という提案です。
当事者同士が対話を重ねて“私の中のあなた、あなたの中の私”を交換し合えれば人類が争わなくてもすむのでは、と企画を始めたころから考え続けてきました。
このパビリオンが、対話を深めることでじわりじわりと人の心に伝わって、そこから世界を変えていくきっかけになっていくと信じています」
それぞれの人に“神回”があるはず、と河瀨さん。テーマパークのような派手な演出はないけれど、自分の心と共鳴して完成する、そんなパビリオンの新しい魅力を感じた。
―愛することはどちらのものともつかない幸せを共にすること― ガラス窓にさりげなく書かれている河瀨さんからのメッセージ