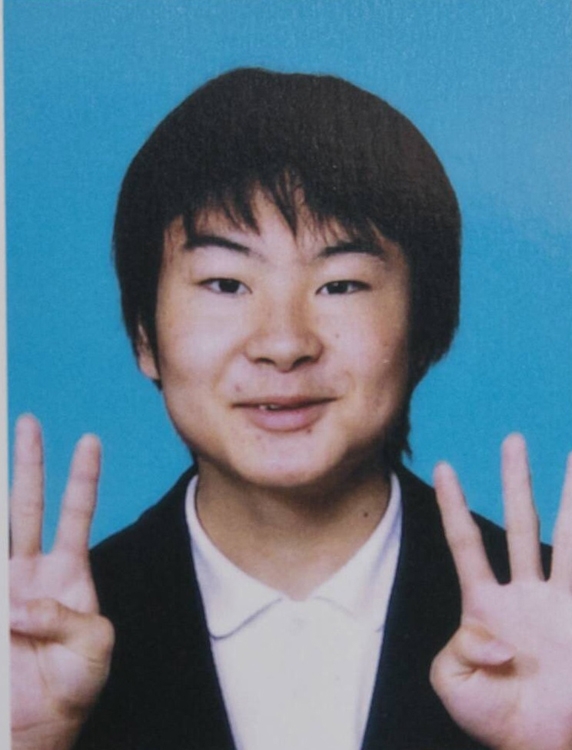凶行に及んだ野津容疑者
部屋に引きこもり、食事は一人で台所で
弁護人から質問がなされる。改めて、被告人の置かれた環境の過酷さを立証していく。
弟から暴力を振るわれシェルターに避難し、音信不通となっていた母親。被告人にとっては母親の不在がむしろ精神的な安定に繋がっていたが、それとは裏腹に徐々に顔を出すようになった母親にストレスが募り、体調に変化が訪れる。
その後は日常生活もままならなくなり、アルバイトも休みがちとなりクビに。大学は休学し、部屋に閉じこもるようになる。外出は週に1〜2度、自身の食料を買いに行くのみだった。家族による食事の提供はなく、自身の金銭で買ったものを、台所で一人で食べていた。費用は一般社団法人からの教育支援金や、大学の奨学金を充てた。家族はそんな様子を心配することも、部屋に様子を見に来ることもなかったと主張する。
無作為に選ばれた裁判員からも、積極的に質問がなされた。その中で特に印象的であったやりとりを引用する。
裁判員「社会からきちんと助けを得られていないように思うが、そこに不満などは」
野津被告「……もう少し詳しく」
裁判員「病気に悩まされ、家族から教育を受けられていない。そんな中、助けを求める先があったと思うのですが、その支援がなかったことに不満はないのですか」
野津被告「……特にないですね」
数秒、間が置かれた上で答えた。筆者は、支援を求めるということに選択肢、可能性が思い浮かばなかったのだろうと感じた。
この裁判員の質問を補足するように、裁判官から質問された。
裁判官「殺害方法をネットで調べる中で、あなたを助けてくれる第三者、公的機関を調べたことはありますか」
野津被告「霊媒師の方に相談したことがあります」
裁判官「公的機関は?」
野津被告「医療は受診しています。それでも解決しなかったので霊媒師に相談しました」
犯行を決断した意思決定は非難されて然るべきであるが、いくらインターネットが発展し、福祉の影響力が増している昨今であっても、当時大学生だった被告人が公的機関の福祉情報に到達するのは困難だったのではないだろうか。制度的な課題点が垣間見えた瞬間だった。