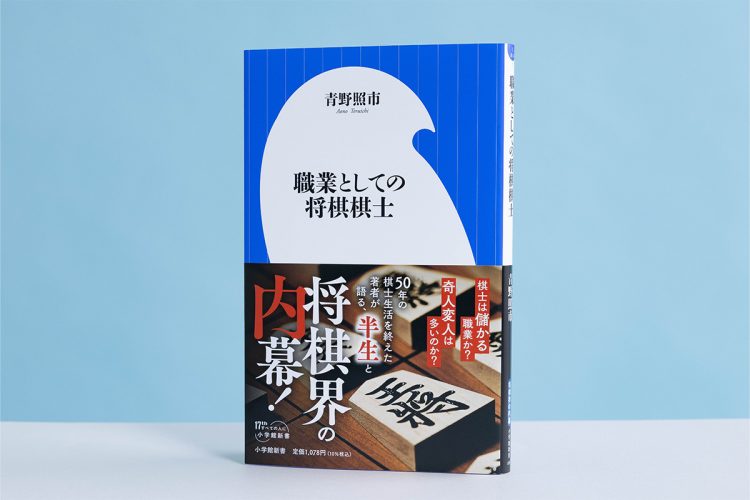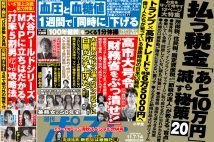棋士人生を振り返って書き下ろした新書『職業としての将棋棋士』
棋士になれる子、なれない子 その「分かれ目」とは
──最近は、藤井聡太七冠の影響なのか、将棋をする子どもが増えていると聞きました。
もちろん藤井七冠の影響は大きいです。ただそれだけでなく、近年は全国で子ども将棋教室が盛況ですし、子どもの大会も増えています。たとえばJT(日本たばこ産業)さん主催の「将棋日本シリーズ テーブルマークこども大会」には、毎年1万人も参加しているんですよ。
──それだけ増えれば、プロ棋士を目指す子も多いのでは?
ええ、増えています。その分、昔よりはるかに厳しくなりました。今は大会で優勝した子でも、小学生で奨励会に入れなければプロになれないことも多いんです。
──そんなに厳しい世界なんですか。
だから私は、棋士を目指すお子さんや、その親御さんに言うんです。「プロを目指すなら、早く奨励会に入った方がいい」と。小学6年までに奨励会に入れば、高校卒業までに6年あります。そこで三段まで上がれなかったら、大学進学を勧めます。そして、高校卒業までに三段に上がっても、大学を卒業する22歳頃までに四段に上がれなかったら、プロは諦めて就職した方がいいと言う。昔のように、中卒や高校中退で奨励会に入り、結局26歳でプロになれなくて退会したら、就職もままならないことが多いですからね。大学にいっていれば、プロを断念しても就職先はあるだろうと。その後の人生が違ってくるんです。
──ただ、将棋と学業の両立は大変そうですが。
それが、小学生からプロを目指すような子は、最低限の勉強しかしていなくても、大学にいける子が多いんです。成績のいい子が必ず棋士になれるわけではないけれども、将棋を鍛えて強くなった子は、たいてい学校のテストは良くできます。特に理数系に強く、難関大学に進む子も多いですよ。
──将棋で子どもが身に付ける力もありそうですね。
ええ、将棋は集中力や忍耐力、記憶力を自然に鍛えてくれますし、論理的思考力も磨かれると思います。勝負の世界で生き抜く精神力も鍛えられます。だから私は、「小学生のうちは、塾に通うより将棋で強くなる方が勉強にも役立つ」と言っているんです。
──礼儀作法も身につくのでは。
たしかに、「負けた時には潔く“負けました”と言いなさい」と教えられますからね。
──自分の負けを認めて「負けました」と口に出す。普段はなかなかない経験ですね。
そう。政治家にも言いたいですよね。うまくいかなかった時に嘘などつかないで、潔く“負けました”と言いなさいって(笑)。
(後編に続く)
構成/真田晴美 写真/五十嵐美弥(小学館)