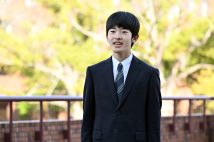なぜ次世代の党は惨敗したのか。諸説あるようだが、最大の理由は「投票率が低い選挙だったから」だと私は思う。当選したのは、岡山3区の平沼赳夫党首と熊本4区の園田博之元官房副長官のみ。比例代表では1人も当選していない。田母神俊雄元航空幕僚長や西村信吾元防衛政務次官などを擁立し、ネット保守やネット右翼の人気を集めるかとも思われたのだが、その層はリアルでさほど動かなかったようだ。
できたばかりの党なので、あくまで推測にすぎないが、もしも今回の選挙の投票率が高かったら、次世代の党はここまでボロ負けしなかったのではないか。前回の都知事選では、田母神氏が20代の投票者の24%の票を集めた。年配者には人気がなく、若い世代ほど彼を支持した。
投票率が低かったのは、解散した当人自ら「アベノミクス選挙」と名づける争点がよくわからない選挙だったからだ。ところが、これが「憲法改正」や国防に関するテーマで争われる選挙だったら、都知事選で田母神氏に票を投じた層も動いたことだろう。安倍自民党はもっと票を集めただろうし、それじゃ「物足りない」層は、自民党より右寄りの政党を支持、正義を遂行する者として次々と投票所に向かった可能性が否定できない。
そういう意味において、「選挙の投票率は高いほどいい」≒「投票率が上がればラブ&ピースな世の中の実現に近づく」的なお花畑思考をまだまだしているリベラル層は、世の中そんなに甘くはないことを、思い知るべき総選挙だったと言いたい。
ちなみに私は、今回の総選挙できちんと投票をした。小選挙区は死票にしたくなかったから自民党と民主党の候補者で迷い、自民党のほうは大物の地盤を引き継いだ元リクルート社員の若手というだけで何のメッセージ性も伝わってこなかったので、民主党候補のほうがまだマシだと思って入れた。結果は、入れたほうが落ちた。ちょっと悔しかった。
比例代表はどの党の政策も気に食わず、棄権も考えたが、どうせならということで、腰の引けたマスコミが増えている中、権力のチェック役としての共産党に入れた。躍進したが、実は政策も体質も自分には合わない党なので、選挙後に彼らが喜んでいる姿を見てもあまり気分はよくない。ただし、共産党の議席がある程度確保されることは、国会という生態系のバランス維持にとって有意義だと思っている。
それに、これまでのように積極的棄権をしたら、「ちぇっ、戦後最低記録といっても半分以上は投票しているじゃん」と疎外感をこじらすだけだっただろう。無理矢理でも投票に行ったことは、個人的に良かったと思っている。