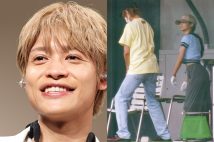◆テレビ放送終了後の「砂埃」は案外眠れる
――「隙間」に「揺らぎ」、眠る時の音っていうのは抽象的で難しいですね!
河合:う~ん、メロディではないんですよ。これは安心感だと思うのです。押し付けない程度の、遠くの方で音が聞こえるくらいがいいです。聞こえるか聞こえない程度の音があると眠れると思います。「ホワイトノイズ」というものがあります。これは「大辞林」では「あらゆる可聴覚周波数帯域の周波数成分が含まれているノイズ。発振器で生成し音響測定に用いるほか,シンセサイザーの音色合成などにも使われる。白色雑音」とありますが、集中力が高まるともされています。
具体的には雨と似たような音ですね。あとは、テレビの放送時間が終わった後の「砂埃」とも言われる「ザーッ」という音もそうです。余計な音が睡眠導入を阻害しないよう防音室に入ってみて寝ようとした事があるんですよ。それなのに、寝たくて入ったというのに眠れない! 無音だと不安や違和感で眠れないんです……。やっぱり「隙間」が必要でして、無音の空間が何らかのノイズ等で埋められている事で人は安心して眠りに入れるのです。
――確かにそうですね。私は昔、田んぼのあるあたりに住んでいたのですが、ウシガエルの鳴き声とか虫の鳴き声が聞こえてきたら確かにすぐに眠れたように思います。今は幹線道路沿いに住んでいるのですが、車が「シャーッ」と走っていく音は案外心地良い。でも、マフラーを外したバイクが「ウィーン、ウィーン」とエンジンをふかしていたりするのは眠れなくなる。そういうことですか。
河合:そうですね。元々「眠れる音楽を作ってくれ」なんて言われてもピンとこなかったんですよ。作っているうちに睡眠については色々考えるようになり、「これは耳に痛いかもしれない」などが分かるようになりました。そこで音質を替えたりして耳障り、心地よさを体感しながら眠れる音に近付けていったのです。
だから、眠るために音楽があった方がいい、とは発想になかったです。しかし虫の音、部屋の中を空気が通過している感覚などは眠れない人向きだなと今回の仕事を通じて感じるようになっていきました。自分も今回の音楽を聴いたらよく眠れるな、とは思いましたね。
◆ヒグラシとクマゼミの違いはどこにあるか?
――「間」とか「隙間」とかはありますが、でもさすがにロックでは寝られないですよね。クラシックではけっこう寝てしまうんですけど。
河合:人工的に作られた音以外に、機械的に並んだドラムの音とか、リズムを刻むのとかは興奮してしまうので寝られませんね。自然界の音は別として、不定期な音が揺らぎをもたらし、空間を埋めるのと、忘れてしまいそうな間で何げに音が鳴るとか心地よさをもたらします。クラシックは今回アプリに組み込んだように、リズムを定期的に刻んだりはあまりしないから眠くなることもある。あとは自然音ってものは、基本は癒されます。お母さんの子宮の中の音と同じような音です。それは心臓音もそうですね。
――自然音にしても、たとえばセミの鳴き声でいえば、クマゼミはけたたましく「シャーシャー!」って鳴き、ヒグラシは「カナカナカナカナ」と静かに鳴く。ヒグラシの音で眠る自信はありますが、クマゼミで眠れる自信はありません。
河合:クマゼミは単にうるさいですね。ディストーション(ひずみ)がかかった音とかは眠れません。ヒグラシは地についた安堵感というか、これは簡単な話で「穏やかさ」です。子供の頃から聞いている音で安堵感があり、寝られます。
――だったら眠れない音楽を作ることはできますか?
河合:すぐ作れますよ! イヤな音楽、誰もが嫌いだって言うものを作るだけです。でも、眠れる音楽は難しい。眠れる音楽というのは、逆説的ではありますが、「どう耳につかないか」ということを考えるのです。眠れる音というのは「定期的」心臓音みたいな自然界の音もあり、不定期で聴いていることを忘れるぐらいな間のある音。遠い位置から、近いけど鳴っている事を忘れる音量、耳障りではない、ほぼ無音に近い音です。制作中、弾いてみて、家で聴いて、家族に聴かせたり、友達に聴かせたりし、次の日聴いて、もう一回――。こんなことをやり続けてきました。どうすれば心地よさを感じられるか、を繰り返し見直しました。眠れない音をつくる事より難しいと思います。
――でも、音楽家として作ったのに、「聴いている実感がない」というのも寂しい話じゃないんですか?
河合:ガハハハハ! やっている方としては聴いてほしいけど、聴き入ってしまったら寝られなくなるじゃない。物音が聞こえないぐらいがいいし、言えば飽きてしまうほどの内容で、ともかくつまらなく作ればいいんですよ。決していいかげんには作っていませんが。むしろ大変でした! なにものも邪魔しない心地いい音を作るってのは本当に難しいことでした。