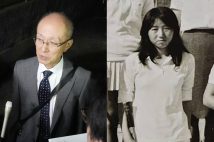まず、タワーマンションを作り過ぎている。私は近々『限界タワーマンション』(集英社新書)という著書を上梓するが、20階以上の超高層マンション(タワマン)という住形態には、大きな欠陥がある。それは、約15年ごとに永遠と外壁の修繕工事を繰り返しやり続けなければいけないという宿命を背負っていることだ。
足場を組めないタワマンの場合、外壁の修繕工事には多大な費用を要する。ざっくりと試算しても通常のマンションの2倍以上。はたして、すべてのタワマンはその費用を負担し続けられるだろうか。
また、街が活気を保つには住まい手の新陳代謝が必要だ。つまり、世代交代。ここで育った人が、自分の子育てのために帰ってくる──というストーリーが生まれる街が理想だ。例えば多摩ニュータウンにはそれがないが、果たして豊洲ではそれが生まれるだろうか?
そもそも豊洲という街はかなり交通利便性が悪い。公共交通としては前述したように地下鉄の有楽町線が使えるが、東京メトロの中でもかなり新しいほうなので、他の路線との接続が悪い。
そのため、本来この街はオフィス街にはなり得ないのだが、現状はオフィスビルが立ち並び、稼働している。街を歩くとビジネスマンらしき人々も多く見かける。また、新しいオフィスビルも建築中だ。
現在、東京の都心は様々に再開発が行われている。渋谷、虎ノ門、日本橋、大手町……。そういった場所は、ここ10年ほどで街の様相が一変するほどの変貌を遂げている。空は狭くなったが、オフィスの床面積は飛躍的に増大した。
その一方で、この国はとてつもない人手不足に見舞われている。ここ2年ほど、渋谷エリアではオフィス需要が供給を上回って、賃貸料金がかなり上昇した。その理由は「人気エリアの綺麗なオフィスなら社員募集で人が集まりやすいから」だという。
都市が膨張する時期には、業務都市も分散する。一時期は多摩ニュータウンや筑波、幕張新都心などに本社機能を移転する動きがひとつの潮流を作っていたが、今はそうではない。むしろ都心回帰だ。
これだけネット社会が発展したにもかかわらず、人は所詮生身の生き物なのだ。いかに優れた通信機能を使ったとしても、フェイス・ツー・フェイスには勝てない。だから、不便な豊洲のオフィスビル需要もいずれは萎むだろう。