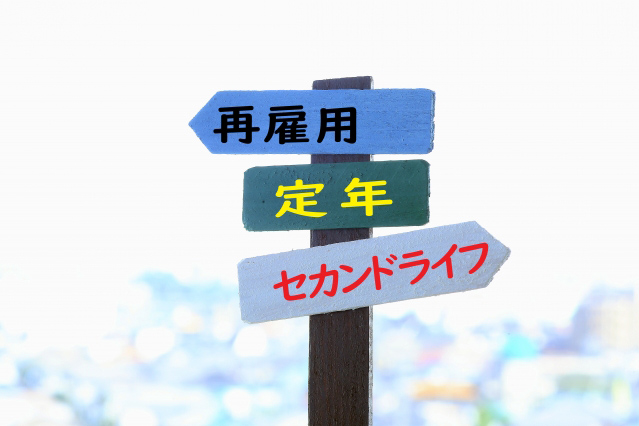定年延長でリタイア生活の期間も限られてしまう
◆「70歳就業」でバラ色の社会になるのか
これまでの定年延長の歴史をみても、最初は企業への努力義務だったのがやがて義務化されていった。それでいくと70歳就業(70歳定年)も数年先には義務化される可能性が十分ある。
2018年の平均寿命は男性81.25歳、女性87.32歳。とはいえ、自立して生活できる年齢を示す「健康寿命」は2016年時点で男性72.14歳、女性74.79歳である。70歳まで働いた後に自由に過ごせる“リタイア生活”の期間は極めて限られてしまう(すべての人がリタイア生活を送れるとは限らないが)。実質的に、「死ぬまで働き続けろ」という社会が迫ってきているとしか思えない。ゆとりも寛容性も感じられない社会だ。
では、現役世代は「70歳定年」をどう受け止めるだろうか。
日経新聞が2019年秋に実施した郵送世論調査によると、70歳以上まで働くつもりだと答えた人が30~50代は3割前後にとどまったものの、60歳代では54%にのぼった。回答の平均値は67.5歳で前回よりも0.9歳上昇し、75歳以上まで働くつもりと答えた人も16%いた。老後の生活のために働き続けたいという人にとっては「70歳定年」でも満足できないということか。
70歳を過ぎても働きたという国民と、「生涯現役」をアピールして「70歳定年」を実現させようとしている政府。高齢者雇用の実現という点では両者の思惑は一致しているが、そうそううまくいくものだろうか。
「70歳定年」が実現すれば、職場での技術の継承という課題の解決につながることは間違いない。熟練技術者の後継問題に悩む中小・零細企業にとっては恩恵を受けることになるだろう。
しかし、サラリーマン社会では高齢の部下が一気に増える事態となる。これは確実にストレスがたまる。逆に高齢者は年下の部下の下で働くわけで、こちらはプライドの問題が出てくる。
職場内の問題だけではない。企業の雇用スタイルが「終身雇用」から「実力主義」「効率主義」へと変化している中で、「構造改革」の名のもと、容赦ないリストラが行われているのが実情だ。