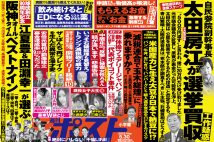大牟田駅の石炭モニュメント
三池の炭鉱は特に大規模だったが、各地の炭鉱でも石炭の採掘により経済的にも活況を呈した。炭鉱のある街は石炭で潤い、そうしたことから石炭は黒いダイヤともてはやされる。
しかし、石炭による活況は長く続かない。1960年代に入ると、石炭は非効率な燃料とされた。新たなエネルギーとして石油が重宝されるようになり、各地の炭鉱は次々と閉鎖されていった。
石炭の需要と供給が細る中、国内屈指の三池炭鉱はなんとか操業を続けた。それでも、1997年に力つき閉山。三池炭鉱の閉山は、国内の石炭産業が幕をおろしたことを意味する。それと同時に、石炭運搬のために建設された三池鉄道は役割を失った。
役割を喪失した三池鉄道は大部分で廃止された。しかし、一部の区間は同じ三井グループの三井東圧化学(現・三井化学)に引き取られて貨物専用線として存続。三井化学大牟田工場に原材料を搬入するための専用線として活用されていた。
生き残った専用線は、わずか1.8キロメートルと短く、同区間を走る貨物列車も1日に数本しかない。そうした状況から、専用線が廃止されるのは時間の問題と目されていた。それでも三井化学専用線は20年以上にわたって物資輸送を担い、地元住民や鉄道ファンからも親しまれる存在になっていた。
しかし、このほど三菱マテリアルが福岡県北九州市にある工場から三井化学大牟田工場への硝酸輸送を終了すると発表。それに伴って三井化学専用線は不必要になり、今年5月末をもって完全に役目を終えることが決まった。
「硝酸輸送を終了した後、専用線の線路や駅、施設などはすぐに取り壊す予定にしていました。専用線は三井化学大牟田工場の物資輸送に活用されていますが、貨物駅として使用されていた宮浦駅や専用線の敷地の一部は日本コークス工業や三井金属鉱業などが所有しているからです。そうした事情もあり、使用停止後はすみやかに敷地を返還する必要があったのです」と説明するのは、三井化学コーポレートコミュニケーション部の担当者だ。