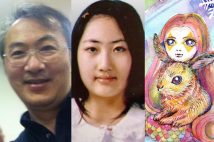2011年、前身の東京市電気局が発足してから100周年を祝う花電車が都電荒川線で運行された。
いずれにしても、華やかな花電車が鹿児島市街地を記念運行することになるだろう。きらびやかな装飾が施された市電が街を走り回る光景を思い浮かべれば、市民でなくても鉄道ファンでなくても胸が弾む。
その前に、来年の2021年は東京五輪が予定されている。そして、東日本大震災の発生から10年を迎える。東京五輪の開催も、東日本大震災からの復興も、日本にとって大きな節目であることは間違いない。そして、2021年は東京都交通局にとっても発足110周年という節目でもある。1930年には、東京市は関東大震災からの復興という名目で花電車を運行したこともある。
都電荒川線の車庫には、2011年に走った花電車が眠ったままになっていた。その後、主だった出番はなく、花電車の専用車両は廃車。荒川線では、その後にも花電車は運行されたが、ペーパーフラワーをあしらった通常車両で代替されている。いくつもの節目と重なる2021年、再び荒川線で花電車が運行されるのでは? との期待は高まるが…。
「コロナ禍ということもあり、人が集まるようなイベントの開催、つまり花電車の運行は現在のところ検討していません。来年は五輪の開催もあってイベントを準備する余裕がない状況です」(東京都交通局お客様サービス課)
花電車の運行は、容易ではない。さまざまな条件をクリアしなければならない。そこには、手間・費用もかかる。そして、沿線住民や利用者の理解も必要になるだろう。それでも、鹿児島市電は運行を続ける。
花電車の運行を続けられるのは、鹿児島市交通局の意気込みも一因だろう。それ以上に、市民がそれを無駄と断じることなく、時代遅れと冷笑しないことも大きい。鹿児島市民からは「市電はわが街のシンボル」「鹿児島市にとって、なくてはならない存在」といった愛着や市電に対する全幅の信頼が窺える。
コロナ禍で、鉄道事業者は生き残りを模索している。なかには、コロナ禍に乗じて廃線という選択肢を迫られている鉄道会社もある。
廃線を迫られている鉄道会社の多くは、普段から利用者が少ない。しかし、理由はそれだけではないはずだ。
各地の鉄道会社が瀬戸際にある中、「経営が苦しくても支える」「日常生活に必要」と鉄道会社を慕うファン層をどれだけ掴めるか? 最後の最後で存廃を決めるのは、沿線住民・利用者と鉄道会社との信頼関係にかかっているといえるのかもしれない。
2007年、都電荒川線はフィルムを貼った簡易バージョンで花電車を復活させた。