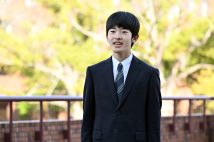義務教育における学習格差は小さかったはずだった(イメージ)
九州地方の公立小学校教頭・森山拓郎さん(仮名・50代)の学校でも、やはり「コロナ格差」が発生しているという。
「緊急事態宣言下での休校期間に親が仕事を休めず、自宅で一人きり、もしくは子供だけで過ごさなければならない子供がたくさんいました。給食だった昼食がカップ麺だけになったりして、登校日に痩せていた子もいました。今度は学力にも差が出てきている」(森山さん)
目立つのは、やはり保護者の収入や家庭環境の違いだ。余裕のある家庭では、自宅に大人がいる時間が確保されており子供の面倒を見られるが、コロナで金銭や時間の余裕がなくなっている家庭の子供は、食事が満足に取れていないだけでなく、学習の機会も減っていると話す。
「学校が休校になったことで、ネット授業が受けられる学習塾に通い始めた子がたくさんいます。一方でパソコンも買えない、という子たちもいて、教員はなんとかその差を埋めようとしていますが、限界を感じています」(森山さん)
実際に、昨年初めて緊急事態宣言が発出された直後、書店やネット通販サイトで、学習参考書や計算ドリルなどが品薄になるという現象も起きた。学校に行けない分、自力でどうにかしよう、そう考える親が少なくなかったことを物語っている。だが、今日食べるための金を稼がなければならないというほど追い詰められている家庭では、子供の学習のことなど二の次だ。
「お父さんが飲食店を経営されているというご家庭の子は、経営悪化でイライラしている親に怒られるし、塾に行かせてとも頼めない、図書館も学校も閉鎖されて行く場所がなくなり、家出をしてしまったという事例もある」(森山さん)
世界中を混乱させているCOVID-19という新型コロナウイルスは、人種や年齢、立場を問わず、人類に等しく襲いかかるウイルスだ。だが、学習の機会に関していえば、富める者だけが十分な教育を受けられ、そうでない人は通常の学校での授業が不十分になっている。近年は、東大生の親の年収は950万円以上が過半数という調査結果が話題を集めるなど、裕福な家庭ほどよりハイレベルな学習成果を収められる格差が指摘されてきた。これは高等教育での話題に留まっていたが、義務教育でも露骨にそれが広がり、コロナで顕在化している。それまで普通とされてきた水準以下の学習しかできないという「格差」が発生してしまっている。
「現在では、よほどのことがない限り小学校や中学校までの義務教育、そして高校までの教育は、貧困家庭出身の子供だろうと受けることができていました。ところがコロナによって事情が変わり、そんな義務教育ですら満足に受けられず、学力や基礎教育の底が抜ける危険性がある。この状態に歯止めをかけるには、子供に努力するよう呼びかけるだけではなんの効果もなく、親の経済力の立て直し、家庭環境の正常化から始めなければならないため、学校や自治体などローカルな環境で努力すれば解決する性質の問題でもない。日本全体が教育の危機に陥っている可能性もあります」(森山さん)
ただでさえ感染拡大を過度に怖れる大人たちから「外で遊び回るな」と制され、子供達の自由は明らかに奪われている。そんな状況に輪をかけるように顕在化しつつある学力の格差問題。「コロナだから」では済まされない、大人や行政の問題であるはずなのだが、この事実に目を向けようとする人は残念ながら少ない。希望溢れるコロナ後の世界の未来を思い描いても、こうした問題の解決なしでは到来は見込めない。