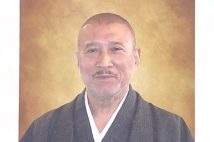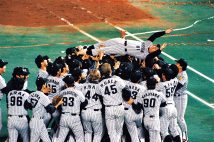ソウルの日本大使館前に設置されている少女像(時事通信フォト)
ところで、文部科学省は8日、教科書出版社5社が提出した「従軍慰安婦」「強制連行」などの表現を削除・変更する修正申請を承認したと明らかにしました。これは政府が「従軍慰安婦」や「強制連行」などの単語は「誤解を招く恐れがある」ため、使用は適切ではないと閣議決定したことを受けたもの。「従軍慰安婦」は多くの教科書で「慰安婦」に、「強制連行」は「強制的な動員」「徴用」などに変更されます。
実際になにがあったかを伝える上で「従軍慰安婦」や「強制連行」という言葉がベストとは限りません。考え方や立場によって、いろんな意見があるでしょう。今回の言い換えを熱心に働きかけていた人たちや、その声に応えた政治家のみなさんは、どうやら「日本(旧日本軍)の責任をなるべく軽く見せたい」という狙いがあるようです。
言い換えを願っていた立場の人たちは、今回のことで一種の達成感を抱いてらっしゃるのでしょうか。ただ、違う立場の人たちやいわゆる「国際社会」は、もしかしたら、とりあえず言い換えることで印象を変えようとしている姿勢にちょっと呆れたり、逆に「よっぽど後ろめたいんだな」と感じたりしている可能性もあります。
この件は、ムキになって言い換えることのデメリットやリスクをあらためて教えてくれました。ほかの政府関係の言い換えの例とも合わせて、以て他山の石とし、言い換えたらごまかせるという勘違いの罠にはまらないように気を付けましょう(最後の文は「あーあ、情けないなあ」の言い換えです)。