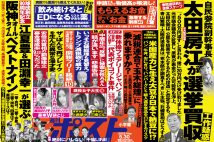上司の承認欲求を満たす場になっていないか
では、管理職や上司はなぜ、そこまでして忘年会や新年会の開催にこだわり、部下を参加させようとするのか。
「職場の一体感を強めるため」「コミュニケーションが大切なので」といった建前の裏に透けてみえるのは、彼らの承認欲求だ。
会食の場で上司は、無意識のうちに自分の経験や価値観を話題にする。そしてアルコールが入ると自慢話にブレーキがかからず、説教じみた話が熱を帯びてくる。
部下の立場からすると、たとえ無礼講だといわれても上司の話に耳を傾け、あいづちを打たなければならない。忘年会や新年会は上司にとって承認欲求を満たす場だが、部下にとっては満たしてあげる場に過ぎない。
忘年会は上司の承認欲求を満たす場になっている
少し踏み込んで考えると、背景には日本の組織や社会に対する一つの誤解があることがわかる。
欧米では管理職は個室に入って仕事をするし、プライベートでも部下とあまり関わりを持たないのが普通である。対照的に大部屋で部下と一緒に仕事をし、飲食も共にする日本の管理職は平等主義的、民主的だと評価されることが多い。
しかし部下と場を共有するからといって、上下関係がなくなるわけではない。特にわが国では、上司と部下の関係は単なる役割上の上下関係にとどまらず、人格的な要素を帯びている。役割の序列は「偉さ」の序列でもあるのだ。
同じ場所で仕事をし、飲食を共にすることで上司は自分の「偉さ」を見せつけられる。場を共有することで「差」が意識させられるのだ。
それでは上司にとって楽しいかもしれないが、見せつけられる部下はたまらない。若手から敬遠されるのも当然だろう。