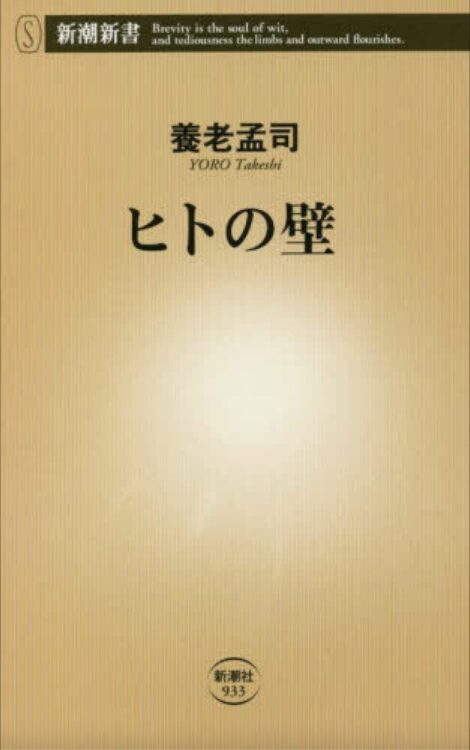養老孟司著『ヒトの壁』
とはいうものの、2020年6月には、体調を崩して久しぶりに病院で検査を受けている。心筋梗塞と診断され、即入院となった。退院後、療養中で時間があるだろう、ということで、編集者からこの本の執筆を依頼されたのだという。
これまでの「壁」シリーズは編集者の聞き書きだったが、今回の本はステイホーム期間中ということもあって、みずから筆を執っている。
「聞き書きの本を何冊かつくって、書いてもらっても自分で書いても、だんだん同じになってきた気がしますね。コロナの前は、人と話しているうちに自分の考えていることがだんだんまとまってきたんですが、ぼくが基礎疾患持ちということで訪ねてくる人も減りました。人と話して考える機会がなくなったのは残念です」
まったくないわけではなく、週に1回は、昆虫好きの仲間たちと、オンラインでおしゃべりしているそうだ。
子供に感想文を書かせるのはおかしいと思いませんか?
何かひとつ、引っかかったことがあると、そのことをずっと考え続けるという。
「異常にしつこいです。言葉の伝わり方の問題や、教育の問題は特に考えます。
国語の授業で子供に感想文を書かせる、あれ、おかしいと思いませんか。具体的に何が起きたかを記すことはやらせず、どう感じたかだけ書かせるなんて。
ずいぶん前から気になっていたんですけど、あるとき、国際学会で、イギリスの解剖学者が『論文というのはドキュメントだ』と言ったんです。自分が考えた立派なことを書くもんだとぼくなんかもどこかで思ってたけど、彼が言うには、そうじゃなくて、実験室で観察した記録なんだ、と」
感想文になっているのは、日本の新聞記事も同じだ、と言う。痛烈なジャーナリズム批判に思えるが、一方で、社会の中で、理性は学者、自由意志は政治家や資本家、良心はジャーナリズムにあたる、とも指摘する。
「他人の顔色をうかがい過ぎていないか」という、『ヒトの壁』の帯文にもとられているこの問いかけは、コロナ禍で、一層胸に響く。
「他人の顔色を気にするということでは、日本人はたぶん世界で一番でしょう。なにしろ居住面積あたりの人口密度が世界一ですから、ぎゅうぎゅう詰めの混んだ銭湯で暮らしているみたいなわけで、何かすると人の迷惑になるのはたしかですからね」