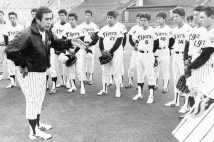捕手の及川(写真右端)は大学で野球を続ける選択を
5回と6回にも柴田は失点を重ねた。途中、捕手の及川恵介がベンチの投手陣に準備を指示していたが、監督は頑として動こうとしない。
大船渡の劣勢は続いた。無我夢中で花巻東打線と対峙するしかなかった柴田と違って、他のナインには動揺が走り、不信感を募らせる者もいた。佐々木とは高田小学校の同級生で、同じ3年生のタイミングで野球を志した及川はこう振り返る。
「(佐々木が)投げないとは思っていなかったので、ビックリしました。朗希としても投げたかったはずですし、もし朗希が投げていたら、勝算ももっと高かったと思う」
國保は佐々木や及川に対し、登板回避の意図を詳しく説明することはなかった。そして、柴田の先発についても、女房役を務める及川に相談することはなかった。
「朗希が投げないにせよ、マウンドに行くのは2番手、3番手のピッチャーかなと考えてはいました。國保先生の考えをもう少し知りたかった。それは自分だけでなく他の選手も思っているはずです」
主軸の外野手・木下大洋は、あの日の試合後、言葉を慎重に選びながらも國保への不満を誰より口にしていた選手だった。
「僕は試合の途中から朗希を投げさせると思っていた。試合中、『なぜなんだ』という気持ちは消えませんでした。あの時点で、北海道日本ハムが朗希を1位指名すると公言していましたよね。つまり、朗希がプロに行くことは決まっていた。ところが、朗希以外の選手は、大学で野球を続けられるかどうかが懸かっていて、甲子園に行くか行かないかで、天と地の差があった。勝利を目指しているのかなと疑問に思うことはありました」(木下)
(後編につづく)
【プロフィール】
柳川悠二(ノンフィクションライター)/1976年、宮崎県生まれ。2016年に『永遠のPL学園』で第23回小学館ノンフィクション大賞を受賞。新著『甲子園と令和の怪物』で、“佐々木朗希以降”の高校球界の新潮流を活写した。
※週刊ポスト2022年8月19・26日号